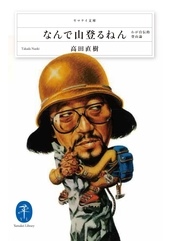
ヤマケイ文庫『なんで山登るねん』表紙
『なんで山登るねん』が初めて単行本になったのは1978年3月のことだった。その後、版を重ねたが、2002年には河出書房新社から文庫本が出た。
今回の「ヤマケイ文庫」出版までに36年が経過しており、かなりのロングセラーといえるだろう。
36年の間には、この本に関しては色々のストーリーがあったのだが、そのうちの一つを紹介する事にしよう。
この本は、山と渓谷社の月刊誌『山と溪谷』の3年間の同名タイトルの連載をそのまま単行本にした物だった。連載中より若者読者から圧倒的な関心をもたれていたようだ。こんな話を聞いたことがあった。
ある人が夏山の帰り、富山駅前の喫茶店に入ったという。すると、そこに数人の高校生が口角泡を飛ばして猛烈な勢いで激論を戦わせていた。何事かと思って耳を澄ますと、『なんで山登るねん』の内容についての議論だったということだった。
もともと一年契約の連載だったのが、ずるずると延ばされたのか伸びたのか、結局3年間の連載となった。1979年12月号の最終回には、「*この連載は間もなく単行本になります」という予告がされていた。単行本の出版を待つ読者が多かったのか、翌年の3月に出た本はあっという間に売り切れになった。8000部が一週間で売り切れになり、編集長のセツダさんは「社では新記録です」と嬉しそうに言った。どんどん売りに売れたようだ。
今手元にある古本で買ったものを見て調べてみると、半年ほどで5刷りを重ね二年ほどで11刷になっているのが分かる。
前置きが長くなったが、タイトルの「差別文書」のエピソードに入ることにする。
たぶん連載が3年目に入ってからの号だったと思うのだが、何月号だったかは覚えていない。タイトルは、<「食いのばし」を知らない世代と「サバイバルごっこ」>だった。その頃はファックスもなかったから、原稿は郵送だった。締め切りぎりぎりの夜が白む頃に、車で京都駅前の中央郵便局に駆けつけ投函するのが常だった。
その原稿を投函してから、あまり推敲していないその原稿で気になっている箇所があった。
すぐに校了となるはずなので、ぼくは慌てて電話して編集長にそのことを伝えた。彼は「でもそこを変えたら面白みがなくなりますよ」と反対だった。そこでぼくは、「タメクニさんに相談してみて。彼がいいと言ったらそのままで、駄目と言ったらぼくが言ったように変えてくれ」と言ったのだった。そう言ったのには理由があった。
タメクニさんは、『岩と雪』という季刊誌の編集長で、ぼくはそこにも記事を書いていたから、彼が天皇を扱った記事を載せて、右翼に怒鳴り込まれて困ったことをよく知っていたからだ。
掲載誌が送られてきて、タメクニさんがぼくの意見に賛同したことを知ったのだった。
一体どう書いてあって、なにが問題だったのか。みなさん、少々イライラしていらっしゃるかもしれません。もう少し待ってください。
その年で連載が終わり、翌年単行本が出ることになった。最終回掲載の12月号は、11月には刊行されているから、暮れにはもう単行本のゲラは出来上がっていた。
ぼくはそのゲラを持って、信州のみそらの団地の友人のスキーハウスに行き、毎日スキー場から帰るとゲラ校正に明け暮れた。
驚いたことに、あの問題の箇所が、元原稿のままに復活していた。記憶が定かではないのだが、たぶんぼくはそのことをセツダさんに言ったと思う。彼はやはりあの時と同じように答えた。変えたことが不本意だったのか、あるいはある人の言によれば、他の人がぼくの考えに賛同したのが気に食わなかったのか。
とにかく、単行本では最初の内容のままで出版されたのだった。
何ヶ月か経った頃、京都でお酒を飲んでいた時だったと思う。セツダさんは勝ち誇ったように「ほらごらんなさい。半年経っても何の文句もつかないでしょう」といった。
いよいよここで、その箇所を引用することにする。『なんで山登るねん』初版本からOCRで読み取ったものである。
< 大学の山岳部には、こうしたいたずらの名人がたくさんいて、ぽくもその影きょうを受けたのかも知れません。ヨシユキなどは、大の名人でした。
いつだったか、冬の合宿の後で、細野部落に回って、八方でスキーをしての帰りのことです。
バスはスキー客ですぐ満員になり、大きなザックを背負ったぼく達は入れません。でも、混んでいるのは入口だけで、中の方は空いています。ヨシユキは、車掌と一緒になって、「すみません。つめて下さい」と頼んでいますが、一向に入口は空きませんでした。見送りにきていたスキー部の「シャモ」がタイミングよく、「ガンバレ、チョウセンひげ」とはやしました。その瞬間、ヨシユキは、破れんばかりの大声でどなったんです。
「チョウセン、チョウセンとパカにするか」
信じられない位、あっという間に入口はガラガラになりました。
バスに乗り込み、「発車」とバスが動きだすと、ヨシユキは、「みなさんどうも御協力ありがとうございました」とあいさつしたもんです。不快な沈黙がただよっていたバスに笑いが湧きました。>
どこが問題だったかは、皆さんお分かりでしょう。
それでは、訂正された雑誌はどうなっていたかって。この「チョウセン」の部分を「ナマズ」に変えていたのでした。確かに少し意味が通らない感じですよね。
初版が出版されて半年ほど経った頃だったと思う。勤務している高校に、高槻のなんとかいう会から電話が掛かってきた。
実は先生の著書の内容に関して山と渓谷社に抗議して、訂正を求めているのですが、まったく取り合ってくれないのです。先生の方から言って頂けませんか。そういう丁重な物言いだったので、ぼくは少々あっけにとられながら、おっしゃる通りです。書き直しましょう。山渓には早急に連絡を取ります。そう答えたのだった。
この会は在日朝鮮人の会で、三省堂の辞書の回収と書き換えをやらせた過激な集団だということが分かった。
ぼくの要請で山渓のセツダさんと出版本部長の二人がやってこられて、たしか高槻の公会堂で糾弾会みたいなことが行われた。東京勢は陳謝するという態度ではなかったし、回収要求にも応じなかった。だから東京の二人は激しく攻撃されることになって、ぼくの方へは攻撃はなかった。ぼくは最初から申し訳なかったと言っているから攻めようがなかったのだろう。
この会の一人の女性は、『なんで山登るねん』はいい本です。私は大好きです。などと敵か味方か分からないような発言をしたりした。また、この本に登場するぼくのザイル仲間のセキタの話では、この会の親玉の男は中学の時の教え子だったそうだ。
この時には、たぶん主催者が呼んだのだろうが、朝日の記者が取材に来ていた。朝日といえば、今と違って賢い人が読む新聞だと思われていた。ぼくもインテリ層の読む新聞だと思っていた。たしかソ連邦崩壊の後ぐらいからだったと思うが、この新聞の連中は全然世界を見ていない分かってないと思い出し、それから何年かして購読を止めて今に至っている。

朝日新聞の記事
「でも、タイトルを付けるのは整理部ですから・・・」
これは気になった。
翌日の朝日には三段抜きの「山男が差別エッセー」のタイトルが踊っていた。
山渓の出版本部長の話として、差別の意図はなかったが配慮が足りなかった。増刷分からはこの部分を削除するというコメントが載った。
著者の高田直樹さんの話として、二十数年前の学生のしたたかさを示すエピソードとして書いたが、配慮が足りず申し訳ない。というコメントがあった。
慰めのつもりか「ベストセラー本だから標的にされたんだ。気にするな」と言ってくれる人もいた。しかし、ぼくは別にめげていたわけではなかった。
増刷分の為の差し替えは実に見事に行われたと思っている。まったくどこを変えたのかさえ分からない。問題箇所のエピソードがそっくり、行数さえ変えずに差し代わっているのだ。
その時はぼくはもう、京都新聞での『いやいやまあまあ』の連載を終えた後だった。新聞連載というのは日曜を除く毎日で、各原稿は厳密に行数が制限されている。
ある決まった行数に、ある話をきっちりはめ込む練習を毎日していたようなものだ。
『なんで山登るねん』の差し替えも上手にやれて当然というものだった。
どう差し代わったのか。次に示してみよう。
< 大学の山岳部には、こうしたいたずらの名人がたくさんいて、ぼくもその影きょうを受けたのかも知れません。ヨシユキなどは、大の名人でした。
いつだったか、冬の合宿の後で、細野部落に回って、八方でスキーをしての帰りのことです。
バス停には、スキーヤーの長い列ができていました。ぼくたちは大きなザックを背にこの列に加わりました。その時、二人のスキーヤーが素知らぬ顔でぼくたちの前に割り込んだのです。ヨシユキは、見送りに来ていたスキー部のシャモに目くばせすると、その二人に近づきました。
そして、二人をジッと睨みつけてから、シャモの方を向き、押し殺した大きな声で、
「シャモはん。正月元旦の誓いは破りますよ」
シャモが、すかさず「なんや、なんちゅう誓いや」と、たずねたものです。
「今年は、もう絶対に人をなぐらんという誓いです」
そういうとヨシユキは、またその二人のスキーヤーを睨みつけたまま、無言で立って’いました。
すぐに、二人はスゴスゴとぼくたちの後に廻ったのでした。>
もう30年以上も前の話である。嫌韓もヘイトスピーチもない時代だった。あれから何年も経ったが、その後ぼくはあんまり変わっていないし、反省したわけでもないようだ。いまでも時々、「チョウセン人というのは・・・」などといい、娘から冗談半分に「まだ反省してないね。あの高槻の会にいうよ」などとからかわれているのです。
