なんで山登らへんの 第17回 1996.9.1
体験的やまイズムのすすめ
![]()

![]()
朝起きて人は朝刊を読む。でもぼくの場合、寝る前に朝刊を読むのが常です。
決してすがすがしい気分でもなく、なかばボーとして、ぺらぺらとぺージを繰りながら、タイトルを見てゆくという感じです。昔からの習慣のせいかスポーツ欄はまず見ません。
不思議なことにこのごろは、昔はおもしろくもなんともなかった一面に面白いタイトルが並んでいると思うことが多いのです。
さきごろのリヨンサミットの時などは、日本の首相もようやく平常の構えで振舞えるようになったと、そのパフォーマンスのような写真を見ながらうれしく思ったのです。これまでの首相は、みんなまるで中国の高官のように、やけに構えてこわばった笑顔あるいは変に尊大な態度などが多いように思っていたからです。
もっとも、あまりに明るすぎるのか、深刻な表情の他国の首相と対照的で、いまの世界が直面している大変な状況の理解が、もしかしてちょっと少ないのではないかしらと、ほんの少々心配になったのですが……。
夕刊と一緒に「ヘラルドトリビューン」が入りますが、こっちの方はときどき写真を見てタイトルをなぞる程度。奥さんは、読みもしないのにお金がもったいないとぼやきますが、「いや読まなくても取ってるだけでいいんだ」とうそぶいているのです。
リヨンサミットの頃の「ヘラルド・トリビューン」一面の写真はぼくの興味を引きました。各国首脳が庭に出てかたまって真剣に議論しています。ところがそのかたまりには日本国首相の姿がない。よく見ると列の後ろ少し離れて、横向きの頭髪だけが隙間から見えているのがそうかも知れません。
あれーっと思って、下の説明をみると〈セブンリーダーの集団が金曜日のリヨンで写真のために並んだ〉とあり、左から順に名前が紹介してあり、最後に〈リュータロハシモトは見えない(out of view)〉とあります。
でも写真にはちゃんと7人が写っている。別の一人は誰なのか。順に名前を追っていっても、ぽくに識別できる名前はクリントンのほか2、3人です。
気になり出すとほおっておけない性質のぼくは、インターネットでリストを打ち出し、順にチェックして、当の人は一番右のヨーロッパ委員会会長のジャクス・サンターと知れたのでした。
この写真本文のタイトルは、「金の首脳会議-貧国援助で険悪な激論」となっているのですが、本文を読んでもIMFの金の分配でもめたようだ位にしかぼくには分かりませんでした。それにしても、日本の新聞の明るい写真を見慣れた目には、異様に気になる写真でした。
先に問題になったエベレストの日本隊の問題では、英国の「フィナンシャルタイムズ」の記事を鵜呑みにしたと、「朝日」を批判した人が多かったようです。
「朝日」のように鵜呑みにするのは駄目ですが、外国紙の記事はどんどん紹介すべきだと思うのです。外国紙の記事を翻訳して紹介するのと、鵜呑みにして記事を作るのとでは大違いです。
いまやインターネットで外国の情報や新聞記事はどんどん取れる時代になった。新聞はインターネットに入れない人のことを考えて紙面を構成すべきではないかと思うのです。
スポーツ記事を減らせとはいいませんが、外国の情報をどんどん報道すべきだと思うのです。読者はきっと喜ぶと思うのですが……。
*
 今新聞をにぎわせているのは、O-157とかいう特殊な大腸菌のようです。
今新聞をにぎわせているのは、O-157とかいう特殊な大腸菌のようです。
だいぶ前、どこかの幼稚園児が井戸水を飲んで死亡するという事故がありました。井戸水が大腸菌に汚染されていたのが、原因という話でした。
大腸菌というのは、誰のおなかにも住み着いている菌のことです。そんなもんで中毒死するなどというのは、よほど細菌への抵抗力のない子どもなのではないだろうか。神経質に泥遊びも許されず無菌状態で育てられた子どもなのだろう。当時ぼくはそう思ったのでした。
ぼくたちが、むかしカラコルムの遠征登山隊でパキスタンにいったとき、そこには赤痢にコレラ、アメーバ赤痢などうようよしていました。生水が危険だなどといっていたらとても奥地には向かえません。
そこで、隊員はカラチやラワルピンディーで気にしないで生水を飲む。するとかならず猛烈な下痢がおそいます。
30分おきに、「あっ、またピッピ、ピッピ」などと陽気にトイレにかけ込んでいる隊員もいれば、意気消沈している者もいました。
ドクターは下痢止めや、イチゴジャム様の便の出るアメーバ赤痢にはエンテロビオフォルム、赤痢にはクロマイを投与する。
いくら下痢がひどくても点滴などはしません。だいたい点滴などというのは、ぼくの理解によれば、水分や食べ物が口から食べられなくなった人に、直接水や栄養を補給するためのもので、点滴を受けるようになったらもう寿命の終わりが近いということ。
いまはどんな病院でもすぐに点滴を行う。もし点滴の保険点数がゼロで点滴の液もうんと安ければあまり流行らないと思うのですが……。ぼく自身あんなものは絶対にいやです。あんな巨大な注射を喜んでしてもらっている人の気が知れない。
さて、パキスタンで生水を飲んで始まった激烈な下痢もだいたい数日、どんなにひどくても一週間もせずに回復します。するともう何を飲んでも何を食べても平気になる。
だからぼくたちはこうした下痢のことを、一種の通過儀礼ととらえ、洗礼と呼んだりしたものでした。
何年か前、ぼくは家族を連れて、27年ぶりに最初のカラコルム、ディラン峰の麓のミナピン村を訪れました。
ちょうど大豪雨のあとで、道路が寸断されてギルギットの病院に行けないとかで、大勢の赤痢や疫痢の病人が薬をもらいにやってきました。
ぼくは家族が感染しないように気を使い、極度に神経質に手の洗い方を教え込みました。
手の洗い方は、外科医のタカヒコドクターのやり方の見よう見まねで、昔から習得していました。
そして薬をもらいにやってきた病気の村人には持参した抗生物質を与えていたのです。
幸いにも誰も感染することなく、無事にカラコルムを後にすることが出来たのでした。
その翌年の夏、友人3人と一緒に、今度は中国からクンジェラーブ峠越えで、ギルギットに出るときにミナピン村に泊まりました。
気をつけていたはずなのに、同行の二人がやられました。なあに薬を飲めば大丈夫、と思ったのは大誤算で、昨年あんなによく効いた薬は、今回は全く効かなかったのです。
この村の菌が、ぼくの薬に耐性を獲得していたということなのでしょう。
日本の病院では、どんどん薬を与え、その結果どんな薬も効かない強力な耐性菌が病院に存在することになる。これが大問題の院内感染というもののようです。
せんだってアマゾンの奥地で発生した、エボラ出血熱はウイルスが原因で、その発生のきっかけは森林の伐採にあるといいます。
O-157もウイルスに感染した大腸菌だそうです。個人あたりの薬の消費量が世界でもっとも高い薬漬けの国はたぶん日本でしょう。だからO-157が日本に大量発生した原因のひとつには、薬漬けの現状が何か関係しているのかも知れません。
給食に原因があったという事で、現場は大変のようです。テレビでは先生が、たぶん消毒液なのでしょう、ポリタンクを持って一列に並んでやってくる学童の掌に一人ずつ注ぎかけています。
いやあ、学校だなあと思ったことでした。これでは、学校はちゃんとやってますというパフォーマンスでしかない。子どもに石けんで手を洗うテクニックを徹底的に教え込むべきです。そうしたテクニックを身につけて初めて子どもは自分の身を守れるようになる。
消毒液に頼る思想というものは、新たな病原菌を誕生させ、滅菌産業などという不健康な産業を太らせるだけだと思うのです。
*
さて近年、医療の問題が話題になる事が多くなりました。
HIV訴訟や新薬問題。もともとぼくからすれば、こんな事が起こるのは極めてよく分かる話で、当然至極という気がするのです。
だいたい日本のお役人あるいは官にはまず 民衆あるいは民を救うというような発想はあまりないようです。
ふつうの国では、官と民は縦並びではなく横並びというか、上下関係は無い。
中国と日本だけが縦並びのようです。中国とその教えを隋唐の時代より受けた日本では、官と民は縦並びそれも遥か離れた縦並びなのでしょう。
最近中国に行く機会が多くなったり、中国人の弟子がいるようになったりで、ぼくの中国理解は急速に進行中なのですが、中国人に関していやだなと思うところは必ず日本人にもある。「一衣帯水。日中友好」ほんとによく似ていて気味が悪いくらいです。
天安門事件の時、「少しぐらいの人間が死んでも問題じゃない」という発言を聞いて、ひどいことをいうもんだと思ったのですが、この国だって正直にいわないだけで、同じではないかという気がしているのです。
ところが、ふつうの国はだいぶ違います。縦並びではないというか官のとらえ方が違う。
何年か前、パキスタン人でアメリカ国籍のカマ-ルが来日し、ぼくの家に滞在したとき、彼は「京都市長に会いたい」といいだし、日本にはそんな習慣がないと説明に苦労したものです。
また、昨年プラハでの結婚式では、パベルが「日本人が初めてここで結婚するのだから日本大使に列席を頼め」といいだし、「日本人の結婚に日本大使が出て当然ではないか」としつこくいうので、これも説明に窮したのです。それで、大使館からの断りの理由は、「大使の親戚縁者ではないので…」というものだったようです。この理由は変ですネ。
パキスタンで通りすがりの高校やカレッジに車を乗り付け、教室のマド越しに授業を参観したいといえば、ほとんどの場合即OKでした。でも日本では、まず駄目です。これは学校が官である証拠。
例の有名な映画『第三の男』の印象的なシーン。高く高く上がった観覧車の中でオーソンウェルズ扮する第三の男が、ジョセフコットン扮する旧友の英国情報部員に眼下に蟻のように小さく見える人の群を指さしていう。
「あの中の一人二人が急に動かなくなったといって何か感じるか」
日本の官は観覧車の中から民衆を見おろしているという構造に置かれているのでないかという気がします。そうであってみれば、この構造が変わらぬ限り同じ様な悲劇は繰り返されると言えるのではないでしょうか。
*
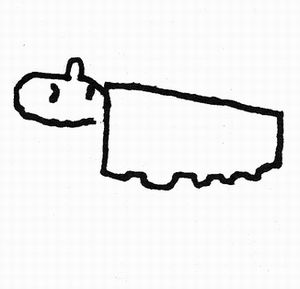 このところ新聞によく「尊厳死」や「安楽死」が取り上げられるようになってきました。
このところ新聞によく「尊厳死」や「安楽死」が取り上げられるようになってきました。
「死」というものを、タブー視することが少なくなってきたという事でしょうか。
ぼくが『なんで山登るねん』や『続々なんで山登るねん』を書いていた70年代、「死」の問題はまだタブーだったようです。
山で死ぬことは、生命の無駄づかいと考えられ、社会的な指弾を受けたものです。
だから『続なんで山登るねん』の「自分の死をデザインするのは個人の自由の問題」の項では、[いまや自分の身体は、自分で管理するものではなくなり、最後は病院の鉄パイプベッドの上で、鼻にゴム管を通されて一生を終えるということになっている」となげき、「自分の死をデザインするのは個人の自由の問題」であるべきだとしながらも、「山での死こそ本望」といいきる自信もなく、「そうかといって、鉄パイプベッドの死もいや」と自家撞着を装いながら煙幕を張り、「まあいずれ死ぬとしても、だいぶ先の話や、あんまり深刻に考えんとこう」と結論を先送りして逃げているのです。
でも、いまのぼくにとっては、それは決してだいぶ先の話ではないし、深刻に考えねばならぬことなのです。
最初にパキスタンに行ったとき、ジャパンクラブ・マネジャーのタケウチさんが、ぼくにこう講義しました。
回教徒にとって、死後の世界は決して別の世界じゃないんです。ちょうどとなりの部屋みたいなもんです。それもドアとかシャッターで仕切られてるんではなくて、薄い布のカーテンです。
彼らにとっては、死とはちょうどすっとカーテンの向こうに移動するのと同じ感覚なんです。回教徒の戦士が強いのはそうした死生観に支えられているからなんですよ……。
下山してきた麓のミナピン村でドクターの北杜夫氏に頼まれて偽医者をやっていたとき、戸板に乗せられたり、背負われたりして、重病の病人が何人もやってきました。病院に入れないと助からないだろうとぼくはいいます。
「インシャッラー」
病人を何日もかかって運んできた人たちは、口々にアラーの思し召しで(助かる)と言い交わしました。病人も落ちついたものでした。
死を運命として受け入れるという態度がすべての人に見られるように思い、これがタケウチさんがいったカーテンの向こうという事なのかと納得したのでした。
パキスタンの奥地の人たちは自分の年齢などにあまり関心がない。年のわずかな差でも気にするのは、日本と中国だけのようなのです。カラコルムの大自然と共に生きる村人は、自分の年齢を、5歳刻みくらいでしか認識していません。
年寄りでも、まるで子どものように陽気にはしやいだりする。寄る年を気にせず死を恐れず、つまり寿命に無頓着に現世を楽しむという態度は、大いに学ぶべきだと思っているわけです。
統計情報部のデータによれば、戦後の歴史の中で、人の死ぬ場所が変わってきたのだそうです。
1950年には、自宅で死ぬ人は90%で、医療施設での死亡はわずか10%に過ぎなかった。ところが、1993年になると、自宅で死ぬ人はわずか23%、77%が病院で死んでいる。
病院というところは本来、生かすために存在すると考えられ、死なせば医療の失敗と考えられた。ハードウェアとしての病院がありハードウェアとしての専門家がいる。そしてここに極めてハードウェアに偏った日本的延命治療が生まれたのでしょう。
そこでは、死ぬべき人が無理矢理に生き続けさせられることになり、こうした不自然さは耐え難い苦痛を生むことにぶる。そして「安楽死」が叫ばれることになります。そして死ぬべきものが生き続けさせられる苦痛は、人間の尊厳さえ奪うので、「尊厳死」が要請される。だから「安楽死」も「尊厳死」も同じことだといえるのでしょう。
ところで、日本で「死のタブー」が消滅し始めたのはだいたい1985年頃と考えられます。この頃になると臓器移植の要請が高まり、それとともに「脳死」の問題がクローズアップされるようになる。「死」を正面切って取り上げざるを得なくなって、そうなってきたといえるようです。
それにしても、最近の京都の安楽死事件みたいなことは、アメリカで20年以上も前に何度も起こったことで、日本はそれだけ遅れているといえるようです。先進国といわれる国はどこでも、医療現場における死に関するシステムを完成させているようで、日本だけはその点では発展途上国レベルかも知れません。
たとえば、ぼくがもっとも先進国だと思うオランダでは、安楽死の実行に至る80ステップが規定されたシステムが完成していて、国民の85%が安楽死を望んでいるそうです。
*
さて、最後にここで、死についてぼくの考えを述べねばならないでしょう。
死とはそれのみで考えられるものではなく、かならず生とセットでなければ死はあり得ない。したがって、生き方があって初めて死に方、つまり死のデザインがあるのだと思うのです。これがいわゆる死生観というものではないでしょうか。
死生観は、死期を知ってから生まれるものではないし、死に臨んで突如現れるものでもない。どう生きるかという思索の中から、一生かかって作り上げられるもののはずです。
そうすると、「自分の死をデザインする」というのは、そう簡単なことではなく一生かかる作業ということになりそうです。
さて、どう生きるかなどといっても、それは極めて禅問答めくので、もっと分解してみましょうか。生きるということには、いくつもの要素があるはずです。
まず呼吸をして心臓が動いてという肉体的なあるいはハードウェアとしての生。そして精神的あるいは心理的な生。また社会的な生活。さらに文化的な生活。
こうした重層的に組み合わされた生をぼくたちは生きています。
いっぽう死もこれに対応して、それぞれの生に対する死があると考えられる。
まず肉体的な死(ふつう人はこれを死としていますが、それはハードウェアに偏った一面的な見方だと思うのです)。つぎに心理的な死。そして社会的な死。さらに文化的な死。
いま行われている延命治療は、あまりに単純すぎて一種の細胞培養のような気がしてきます。
延命治療というものは、人間という総体を対象に行わなければならない。
このようにして、死についての考えを押し進めると、必然的に、死を社会的・医療福祉的に考えるということになってくるようです。
病院で死期が近づき患者の家族が呼ばれる。いよいよ臨終になると、「家族の方は出て下さい」と追い出す病院もあるのだそうです。電気ショックの甦生術などを行うかららしい。追い出さないにしても、そうした病院では、患者の周りに集まった家族がみんなで、死にゆく人の顔ではなく心臓パルスのディスプレイを見つめている。
ハードウェア信仰ここに極まるの図ではありませんか。
逝く人を看取るというのは、その人の周りに位置し、その人の思い出を語る。みんながその顔の変化から死を見とり、医師が脈で確認しみんなに告げるというのが正しいあり方だと思うのです。そういう風にできないというのは、すでに何かが狂っているのではないでしょうか。
定年になり、仕事が無くなると社会的な死を迎える人も多い。もっともそれまでに文化的には死んでいる人もいるかも知れません。
おそらく、文化的社会的な死によって、人は心理的な死をも迎えるのではないかと思うのです。そして心理的な死が、急速に肉体を萎えさせてゆく。
がんばって山歩きをし、そうした肉体運動だけで若さを保てると考えるのはハードウェア志向のもたらすひとつの思いこみに過ぎないのかも知れません。
いきいきと生きるためには、まず精神的にいきいきしている必要がある。精神的にいきいきしているためには、社会的文化的に生きている必要があるのではないでしょうか。
文化的社会的死によって起こった心理的な死、それがいわゆる「ぼけ」といわれるものではないかという気がしています。
だから老人養護施設で行われている、「むすんでひらぁいて」などという幼稚園のようなグループ遊戯などは、老人の尊厳を無視し、「ぼけ」を助長するだけでなく、〈人は品位ある死の権利を保有する〉という「世界尊厳死言言」の精神にも反すると思うのです。
こうしているいまも、死は必然的にぼくに、いやぼくだけでなくあなたにも、その距離を縮めているはずです。
でも、ぼくにとって「あの世」は、回教徒のように、「この世」のすぐ隣にあり、多くの先に逝った山の仲間が「草葉の陰」で待ってくれているはずです。
だからぼくとしては、病院で心電計をつけられて死を迎えるくらいなら、低山の山道での「のたれ死」のほうが、はるかに望ましいと思えるのです。
