<高田直樹ウェッブサイトへようこそ>と同時掲載
なんで山登らへんの 第16回 1996.8.1
体験的やまイズムのすすめ

![]()
 外国にしばらく滞在して、日本に帰ってくると、普段は何ともないことが、やたら気になったりする。
外国にしばらく滞在して、日本に帰ってくると、普段は何ともないことが、やたら気になったりする。
ヨーロッパから帰ってきて、気になるのが町中に林立する電柱と、クモの巣のように走る電線。
いつだったか、パキスタンから帰ってきてすぐの頃のことです。京都の町なかの細い路地から空を見上げたとき、その電線の絡み具合が、ラホールのオールドシティのスラムの路地の電線を彷彿とさせるものだったので、驚くと共に何となくめげたのでした。電柱にしても、日本の細い道を車で走りながら、この電柱がなかったらどんなにスムーズに走れるだろうといつも思うのです。
ヨーロッパでは、ふつう、駅に改札がありません。チケットは車掌がチエックする。
町なかの市電や市バスなどでは、乗車券はだいたい自己申告で勝手に支払う。もちろん抜き打ちの検札があるようですが、でもあんまりただ乗りをする人もいないようです。
もし日本で同じシステムにしたら―まず絶対にそうならないでしょうが―みんな平気でただ乗りをするかも知れません。
日本でも無人のシステムとしては、産地のみかん販売所などがあるけれど、意外にほとんどの人は正直にお金を払っているようです。
ミカンを取って、お金を払わなかったら泥棒。でも身体の移動というだけの形にならないものには、お金を払わなくても平気ということなのでしょうか。形のあるものにはお金を払うけれど、形のないものにはお金を払う気にならない。
日本の都市では、この頃になってようやくヨーロッパのようにパントマイムやフォークソングなどの大道芸で、お金を集める外人がちらほらと見られるようになりました。観察しているとずっと見ていてお金は投げ入れない人がほとんどです。
ただ食いはいけないけれどただ見は許されるということなのでしょうか。
食べた分だけのお金を払わないといけないように、見た分聞いた分だけのお金も払うべきだというのが世界の常識。ただ、それに価値を認めなかったら払う必要はないのです。
物にしか値段の付けられない日本人は、チップに関しても、それが習慣とかマナー・儀礼のように思ってしまう。それが、自分が受けたサービスの質を自分自身が判断評価して支払うもの、あるいは一種の評価システムであるというような理解などまるで無く、至る所でお札をふりまき、馬鹿にされ、ぼったくられる存在となる。
ここでぼくが述べていることは、日本人のソフトウェア音痴ということなのでしょうか。
目に見えない物を、お金に換算する能力、あるいはそうした価値判断の基準となる個人としての自己がない。
物においても、それに内包されるソフトは無視され、ギリシャの彫像も大理石の丸テーブルも同じになり、「なるほどすごい。ワンピースもんや」などということになる。
もう10年以上も前の5月のある日のこと。
ぼくは、ローマのある美術館で初めてみる名作「瀕死のガリア人」に見惚れていました。
するとそばにきた日本人の中年の夫婦づれの夫人の方が、「これはどういうものですか」と聞いたのです。
ぼくは、あまり詳しくないのですがと前置きして、「ほら、このガリア人の瀕死のあえぎの息音が聞こえるみたいでしょう。ガリア人は先住民でローマ人の勝利者の誇りも彫り込まれてるみたいです」
すると、そばにいた旦那が、「フーン、なるほどこれはスゴイ。ワンピースもんや」
継ぎ目のない大理石製品は、ワンピースものと呼ばれ高価なのです。驚きあきれ二の句が継げず、そしてぼくは情けなかったのでした。
*
日本の駅のプラットフォームには、きまって黄色の疣疣のベルトラインがある。ああいう物を設置して事足れりとしている神経はどうかしている。
目の不自由な人がいたら、自然に補助したり介助できるように大衆を教育することが、最重要ではないのだろうか。そんな気がするのです。
電車に乗ると、シルバーシートなる物がある。お年寄り、身体の不自由な人の優先席と書いてあります。でも大抵の場合、若者が座っていて年寄りが立っている。
シルバーシートを設置しただけでは駄目なのです。老人が居たら席を立つように教育し指導しなければ。そして、かなり立て込んできても、シルバーシートは一つ二つはあいているという事になったら完璧で、その時日本は美しい国だといえるでしょう。
15年ほども前のある日曜日、所用で大阪に出かけたぼくが、電車に揺られて、うつらうつらしていると、「おい、そこの青年」という大きな怒声がとどろきました。
ぼくは一瞬ハツとして、自分のことかと思い、次の瞬間「50代で青年はないだろう」と苦笑したのです。
怒鳴ったのは、金茶色の着物を着た60代のどうやらその世界の人のようでした。
「青年、おまえはどうして前の老人に席を譲らんのか。それでも日本人か」
こうしたいかつい老人は、死に絶えて、いまはもういないようです。
もしかしたら、シルバーシートには座りたがらない老人が多いのかも知れません。シルバーシートに座ったら老人になる。
ぼくの考えでは、シルバーシートなんぞ一つも要らない。すべてのシートはシルバーシートであるべきです。
「お年寄り優先席」のお年寄りとは、いったい何歳をいうのでしょうか。
だいたい、お年寄りの年齢をハード的感覚で規定しようなどとはナンセンス。それは自分が基準となって決まる。自分より年上あるいは弱そうに見えれば、それはお年寄りと考えればいいのです。
子どもを座らせ、親が立つなどというのは、言語道断。これは日本だけに見られる光景のようです。
アムステルダムのとある小さなイタリア・レストラン。
お母さんと3、4歳の可愛い坊やとお洒落なおばあちゃんの3人が食事を始めました。坊やのお皿には、何もありません。坊やはじっとして二人が食べるのを見ていました。お母さんとおばあちゃんがお皿の半分ほどを平らげたとき、お母さんが初めて坊やのお皿に自分の半分を移しました。
坊やが食べ終わるのが、少し早かったようです。大人が食事を終えたその時から急にその坊やが、椅子の上で動き出して、お母さんにふざけたりし始めたのです。
ぽくの連れが言ったものです。「ビータスと一緒」
ビータスというのは、ぼくの愛犬で、彼もぼくが食事中は、〈伏せ〉の全くの静止状態を取っていますが、食事が終わって爪楊枝をくわえると同時に膝に登ろうとする。
ヨーロッパのある階層以上の子どもは、まるで犬のようにしつけられているのだろうか。ぼくは驚いてしまったのでした。
日本の場合、子どもはおろか、犬でさえしつけられない。自分をリーダーと思いこみ、ふん袋を手にした家来を連れているつもりのわがまま犬に引っ張られて、散歩に付き添う。これが日本の現状のようです。
ヨーロッパでは、至る所で犬を見かけます。お客を助手席に乗せないパリでは、傍らに愛犬を乗せているタクシーもある。歩いている犬の半分はノーリード(引き綱なし)です。でもけっして駆け出したりしないようにしつけられている。別の犬に行きあうと、友好的に臭いをかぎあい挨拶し、そして別れる。
日本の犬のほとんどは、常に綱で繋がれていないとどうしようもない。散歩で行き会ってもあまり友好的ではなく、時には闘争的な態度をとって唸りあったりする。まるで会社に繋がれ、たまに海外に出ても、同胞に対して決して友好的でない日本人そっくりみたいな気がしてしまいます。’
*
 こんな風に日本や日本人を批判すると、かなりの人が「けしからん」と怒ることはないにしても、気分を害するのではないでしょうか。でももしそれが本当だとしたら、冷静に受けとめて自分なりに解決を図る。そういうことが要求されるような時代になってきているといえるのではないでしょうか。
こんな風に日本や日本人を批判すると、かなりの人が「けしからん」と怒ることはないにしても、気分を害するのではないでしょうか。でももしそれが本当だとしたら、冷静に受けとめて自分なりに解決を図る。そういうことが要求されるような時代になってきているといえるのではないでしょうか。
ぼくは、数日前アムステルダムから戻ってきたところです。昨年、ぼくの息子のプラハでの結婚式をすべてアレンジしてくれた友人のパベルが、今年は自分が結婚するというので、みんなでその結婚式に出席してきたのです。
昨年のプラハでの結婚式は、14世紀に建てられた、あの天文時計で有名な旧市庁舎で行われ、それは荘厳なものでした。
いずれも宗教色をまったく欠いているところは同じなのですが、アムステルダムのそれは、明るく軽快にデザインされた市の公設式場で行われ、実にリラックスした雰囲気で、儀典長のスピーチにも笑いが湧いていました。
その後の300人ほどのレセプションはケーキカットだけで挨拶もスピーチもなく、オードブルとウェディングケーキで部屋の中や外の広い庭でシャンペンを飲む。受付も記帳もなく、サイン帳だけが回ってくるシンプルな披露の集いでした。
ケーキカットの9段重ねのシンプルなウェディングケーキはもちろん本物でした。
日本を発つ数日前、ぼくはあるホテルでの結婚式に出席していました。
司会嬢が「皆様、新郎新婦によるケーキカットでございます」と声を張り上げます。
「この感激の一瞬をフィルムに収めたい方はどうぞ前にお進み下さい」
新郎新婦が、台の上に純白に高くそびえ立つ巨大ともいえるウェディングケーキの裏側に回り、ピカピカと光るナイフを縦に入れました。よく見るとそのナイフの入るところだけが、幅3センチ高さ10センチ位の短冊状にえぐってあり、中にはバターか何かが詰めてあります。高砂の仲人の席に座っていたぼくだけには、はっきりと見えたのです。
なんとそのケーキはすべてがプラスチック製のイミテーションでした。前に駆けつけた何人もの人がフラッシュをたき続け、ぼくはショックで、なにやら象徴的に日本を見たような気分で、思わず目をそらしたのです。
さて、アムステルダムでのレセプションは2時に終わり、3時から80人が帆船に乗ってクルージングを楽しむという趣向でした。
長さが50メートルはあるデッキでは、白ワインと生牡礪が常に供されています。
8時頃になって全員が船室の一室にぎっしりと集まり、スピーチパーティがありました。
薄暗い船室の天井にはIカ所天窓が甲板に開いており、そこがしゃべる人のトッブライトの位置です。
スピーチは新郎新婦の父親に始まって友人6人の計8人だけ。最後にパベルがお礼を述べました。
着物を着てのぼくのスピーチは、「オランダはアメリカのように暴力を用いることなく、日本に交際を求めた国である」と日本とオランダの江戸時代の交渉から説き起こす、自分で言うのも変ですが、格調高いものでけっこう受けたようでした。
スピーチを行ったのはみんな男性で、アメリカにかぶれ毒された日本と違って、つましい女性というモデルがいまも生きているという感じでした。
このマイクを使わないスピーチパーティの問、聴衆が、もちろん半畳も入るし笑いもしますが、実に静粛に話に聞き入っていました。子どもも何人もいましたが、騒いだりはしません。
日本の場合、決してこうはいかない。学校でそう教えていないどころか、学校の教師自身が人の話が聞けない人が多いのですからどうしようもないのです。
もう一つ驚きとともに気づいたことは、3時から始まって11時に終わるまでの約8時間の間、ずっとワインとビールが供されていたにもかかわらず、酔っぱらっている人が一人もいなかったという事実でした。
*
アムステルダムで過ごすと、いろいろと日本との古いつながりに気づいたりすることが多いのですが、とくに思うことは、オランダはやはり大人の国だなあということです。
古い国だけのことはある。日本だって極めて古い国で、ヨーロッパの国が憧れるくらいだったのに、まるで子どものように若い国でそれが売り物のアメリカのまねをして、良いところまでを捨て去ってしまった。
アムステルダムが、ダイヤモンドの世界マーケットの中心であることはあまり知られていません。また原油のスポッ卜買い市場はロッテルダムであることもあまり誰でもは知らない。インターネット上のお金レジキャッシュのビジネスを始めているのもオランダの会社です。ネスカフェがスイスだと聞いて驚く人が多い。お金持ちになった国は、それをひけらかすようなことはすべきでないというのが世界の常識だと思うのです。
香港の九龍サイドに立って香港島を見たとき、その美しい夜景をぶちこわしている約8個の巨大なネオンサインの内7つまでが日本の会社名であるとき、ぼくはいつも吐き気をもよおします。
さて、アムステルダムに「グリーンピース」の本部があることも、あまり知られていません。ぼく自身このことを、つい最近まで知りませんでした。
こんどのヨーロッパ行に持っていって読んだ、山渓のイケダさんが編集した『グリーンピース・ストーリー』で分かったのです。〈訳者あとがき〉にはこうあります。
―ふるくからご縁のある山と渓谷社の、クライマーの牙城『岩と雪』の編集長だった池田常道さんからThe Greenpeace Storyという本を見せられ、「訳しませんか?」と言われて、正直なところ少々びっくりしてしまった。「ヤマケイ」とグリーンピース、という組み合わせはどうもぴんとこなかったのだ―
ぼくは思うには、ヤマケイとグリーンピースがぴんとこなかったのはいいとして、これからは、ヤマケイと環境問題、これは誰もがピンと来るようにならないといけない。
さて、「グリーンピース」というと、日本ではボランティアの圧力団体ぐらいにしかとらえられていないようです。
だいたい、ボランティアも「人助け」の活動という具合にハード的にしかとらえない。老人施設に行って労力奉仕をする。立派なことだから単位をあげなさいなどと文部省が言い出す。
でも、ボランティアというのは、自発性の文化に支えられた自己啓発運動で、生き甲斐論につながるものなのだと思うのです。
*
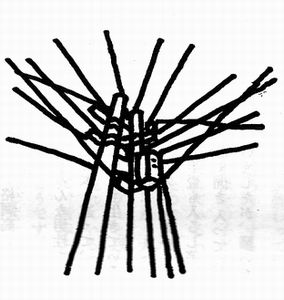 日本でのイルカ救出の実力行動でも知られるように、彼らの活動は過激とも見えます。
日本でのイルカ救出の実力行動でも知られるように、彼らの活動は過激とも見えます。
捕鯨阻止で、キャッチャーボートのモリにわが身を鎖で巻き付け、鍵をかけ、合い鍵を海に投げ捨てるというようなことをする。
〈1984年の6月11日、ロンドンの中心でふたりのクライマー、イギリスの学校教師ロン・テイラーと、チューリッヒから来た登山家のレナート・ルフは市当局を仰天させた。彼らはあのビッグ・ベンの台座に取り付き、55メートルよじ登ったのだ。ふたりは時計の文字盤の前に、「いまこそ核実験をやめるとき」という2メートルの赤い文字を張り巡らせて、その高みに11時間留まった〉
このパフォーマンスは、世界中に連鎖反応のように広がります。
2ヵ月後の8月6日、4人が自由の女神に登り、5時間留まる。この日はヒロシマ・デーで横断幕には「われらに核兵器からの自由を。実験を中止せよ」。
また彼らは大気汚染を阻止するために工場の煙突に登り垂れ幕を掛けます。
1985年3月、2人がイギリスのダイオキサイドUKの工場煙突へ。
1985年4月。4人がアントワープの聖マリア大聖堂の塔の台座に登り、「ヘルプ!直ちに酸性雨をとめて!」の垂れ幕。
1986年12月。4人のクライマーがスイスの化学会社チバガイギーのバーゼルエ場で120メートルの煙突に登る。化学産業の規制を求めての行動。(以上『グリーンビース・ストーリー』より)
もう列挙するのはやめますが、こうしたことをやったのはみんなクライマーなのです。橋の欄干に点々とぶら下がる、いわゆる人間カーテンで、船の通行を止め水質詞査の水の採取を行い、水の汚染を訴えるなどというのは、ユマールに習熟したクライマーでないとできないことです。
グリンピースの会員数は、オランダの20万は本部のある国としてうなずけるとして、日本の2300人というのは、不思議なくらい少ないと言えます。お金持ちの国であっても先進国ではない。
やはりハードウェア志向、ソフトウェア音痴では、自発性の文化としての活動は育たないということなのでしょうか。
たとえば、先頃話題になった日本のエベレスト登山隊に対する「言いがかり論」あるいはとんだ「ぬれぎぬ論」にしても、ぽくにはやはりハードウェア志向の論調と思えたのでした。8000とか8500とかの高度で区切ったり、あるいはヒマラヤという地域で区切ったりする考え方こそが、ぼくのいうハードウェア志向なのだと思うのです。
8500メートル以上は自己責任、つまり死んでも自分の責任だという。でも山登りではどこで死んでも自分の責任です。
山に限らず、どこでもいつでも、人は自分の責任で選択し、その結果は自分で責任をとる。これは世界の常識というべきでしょう。
この国はおそろしく責任のとれない人に満ちているというのがぼくの認識です。
『禿鷹と少女』で賞をもらった外国人カメラマンは、シャッターを切るより少女を助けようとすべきだったという非難だけで、自殺する。一方、校門の鉄の門扉で教え子の女子高生の頭を砕いた教師や学校や教育委員会はその後どうなったのでしょう。
危険な場所に行って死んでもそれは自分の責任。一方、瀕死の人がいたらそれを助けるというのも地球上の公理ともいえることです。
エベレストの超高所で、死に瀕していた人は、けっして助けを求めたわけではなかったと思うのです。そして、そこを通りかかった人も助けるだけの余力は決してなかったし、どだい無理だったのでしょう。
別にエベレストでなくても、ヒマラヤでなくても、何処でも同じ問題は起こる。その時どうするのか。出来なかったことは仕方がないのではないでしょうか。
どうしようもなかったのだ。許してほしい。そう言うしか仕方がないのではないか。
いま新聞紙面をにぎわしているような官界・政界・財界の人々のような言い逃れの物言いは決して必要ないと思うのです。
