国会議員の稲田朋美さんのお父様が講演なさるから行きませんかと誘われた。稲田朋美議員には、おかしげな女性議員が多い中で、大変好感を持っていた。
誘い手は、そうしたぼくの気持ちを見透かしたかのように「この親にしてこの子あり」というでしょと追い討ちをかけて来た。
演題は「新かなはなぜいけないのか」というもので、興味がないとはいえないものだったので、日曜日の午後、四条烏丸の第五長谷ビルに出かけた。
会場には、竹田研究会と同様に日の丸が鎮座しており、そこは「頑張れ日本!全国行動委員会京都府本部連続セミナー」の会場だった。
そう思って見回してみると、桜チャンネルで見覚えの顔が見えた。(谷田川惣氏)
演題は「戦後の国字改革の問題点を考える」というものだった。演者の椿原泰夫氏は洛北高校の校長を勤めた人だったことが後になって分かり、お話をすればよかったと思った。
講演は、詳細な資料が整えられており、いくつかの本の紹介もあって、内容の濃いものだった。椿原先生の話を聞いて、思い出したことがいくつかあった。それについて書いてみようと思う。
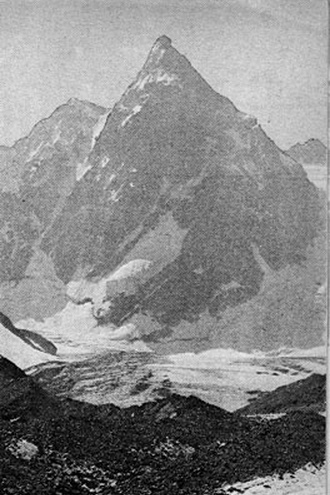
シュロフスキー峰
こういう場合には、海外研修という名目で出かけるのだが、教育委員会が許可を渋った。「この前の時には、青少年に夢と希望を与えるということで行って頂きました。しかし、夢と希望は一回だけで結構なのです」
これには参った。しかし、結局は粘り勝ちで出かけることが出来た。
コーカサス遠征は、この2年後のことだったから、難しいと思われた。しかし、派遣母体が、当時強大であった総評だったから、意外にすんなりと許可が出た。
二回目のスワット地域は、いまはアルカイダの巣窟であるし、三回目のコーカサスにしてもウクライナ地方は紛争地で、いずれもとてもヤバイ地域となっている。不思議にぼくが行った場所は、今はとても物騒な地域となっている。
話を元に戻して、われわれ日本隊の13名は、まずコーカサス山脈のシュロフスキー峰を目指した。インストラクターのボリスと救急隊員の一人が規定によって同行した。
ベースキャンフについた時、隊員の一人が、救急隊員に名前を聞いた。彼は「スタス・ババスキン」と答え、隊員は「そうかそうか。スタス・ババスキンやね」とおおむ返しした。
「ニエット。スタス・ババスキン」
「スタス・ババスキン」
「ニエット。スタス・ババスキン」
この応酬が何回か繰り返され、ババスキンは、とうとうたまりかねた風で、
「ババスキンッヌ」と言ったのだった。
ぼくは、この時に理解した。ロシア語には「n」と「ng」の二つの音素があるが、日本語には「ん」しかないので、区別できないのだと。
もともと、言語には興味があって、最初の遠征時に隊員がウルドー語を覚えて行く過程と自分の子供が言葉を覚えていく様子を対比して、「遠征隊の言語習得について」というレポートを書いたりしていた。
だから、この「ん」の問題に関しても、ずっと気になっていたのだが、日本語にも二つの「ん」があることを発見したのだ。
「神田」の「ん」と「寒気」の「ん」は違う。「ババスキン」の「ん」は「寒気」のそれであることに気付いた訳だ。もし、この違いを国語で習っておれば、ババスキンに「ニエット」といわれることもなかった筈である。
この話をしていたら、夏に沖縄に滞在したという生物教師が、沖縄には「F」音が存在したということを教えてくれた。それでぼくは、本州にも平安時代には、エフ音が存在したという話を思い出した。
平安時代には、母は「ふぁふぁ」だったのだそうだ。それを証明したのは、次のような「なぞなぞ」であった。
ははには二たびあいたれども ちちには一度もあわず。
そしてこの答えは「くちびる」だったのである。
ハ行の子音は、奈良時代以前にはpだった。つまり「パ」だったのが奈良時代あたりから「ファ」になり、そして「ハ」となったのは、江戸時代だという。厳密に言って平安の「ファ」はエフ音ではないという。
椿原先生が、配ってくださった資料の中に、小堀桂一郎氏(東京大学名誉教授)の「いにしえ人の聲を聞く心地」という旧仮名遣いで書かれたエッセイのコピーがあった。
その中の一節は以下の通り。
国語の音韻に造詣深く、その正しい発音に深い関心を有してをられる或る高名なソプラノ歌手が、「冬景色」といふよく知られた大正時代の文部省唱歌を例にとって、その第一節<狭霧消ゆる港江(え)の/舟に白し朝の霜/ただ水鳥の聲(こゑ)はして/いまださめず岸の家(いへ)>に含まれた、え、ゑ、への三音は元来判然と三種の異なる音として発音し分け得るものである、ところが「現代かなづかい」なる戦後の国語破壊工作がこの区別を無視していづれも「え」字で表記することに定めた。そのために現代の児童は国語に三種の「え」音があることを教へられず、結果として耳でも口でもその区別が出来なくなった、と説かれた。そして御自分で右の唱歌の第一節を唱ってきかせて下さったのだが、その歌唱では、え、ゑ、への三音は見事に発音し分けられてゐた。ーーー
この三つの音の違いはどのように表記できるのだろうか。この違いを表現する発音記号みたいなものが作られ、それが国語教育で用いられなければ、そのそれぞれを発音することは出来ず、この仮名遣いは消えてしまうと思われる。
椿原先生は、国語学者・橋本進吉の説を援用して「仮名遣いは、単なる音をかなで書く場合の決まりではなく、語をかなで書く場合の決まりである」とおっしゃったが、ぼくには国語学者が音声学的アプローチを欠いたままであることが、旧仮名遣いの消滅を招いた原因ではないかと感じられた。
何度も見に出かけていながら、都踊りの表記が「都をどり」であることに気付いたのは、大分してからだった。
どうして「おどり」でなくて「をどり」なんだろう。答えはすぐに見つかった。
1946年(昭和21年)11月16日に内閣告示によって「現代仮名遣い」と「当用漢字」が制定され、かなは発音通りに表記することになった。しかし「都をどり」は、その表記を変えることがなかった訳だ。
この時までは、ほとんどの「o」は、「を」を用いていたらしい。発音も「オドリ」ではなくて「ウォドリ」だったのだろう。
今回の講演で知ったのだが、この国字改革の最終目標は漢字の廃止だったという。定められた「当用漢字」の本当の意味は「当座の用に当てる」だったのだそうだ。
つまり「現代仮名遣い」と「当用漢字」の設定は、漢字を撤廃して、ローマ字またはかな文字にすることを目指していた。

 確かにあの頃、それはコーカサス遠征の前だったから、1970年頃だったと思う。かな文字論やローマ字論が盛んだった。かなやローマ字での分かち書きが喧伝されていた。かな文字論者の筆頭だった梅棹忠夫先生がかな文字をタイプする為に、かなタイプを注文しようとされたのだが、日本では引き受ける所がなく、スイスのヘルメスが1000台単位だったら作ろうと言ったそうだ。
確かにあの頃、それはコーカサス遠征の前だったから、1970年頃だったと思う。かな文字論やローマ字論が盛んだった。かなやローマ字での分かち書きが喧伝されていた。かな文字論者の筆頭だった梅棹忠夫先生がかな文字をタイプする為に、かなタイプを注文しようとされたのだが、日本では引き受ける所がなく、スイスのヘルメスが1000台単位だったら作ろうと言ったそうだ。
作らせたのはいいものの、この1000台のスイス・ヘルメス製のかなタイプはなかなか捌けなかったそうで、買いませんかといわれて、けっこう高い値段で購入したのだった。
面白がって、詩や童謡を作ったり、手紙を書いたりしていたのだが、変に奇をてらってるように思われたようだった。
たしかに、リズム感のある文が書けるような気がしたし、とくに擬音・擬態語などで、創造的なものが作れるような気がしていた。
しかし、かな文字・ローマ字論者が唱えるような、思考の深化など望むべくもなかったと思われた。漢字の深さとイメージの広がりを再認識した。
例えば、車三つを積み上げた「轟」を、かなでどう表現しても、その深さ・広さにはかなわない。
そんな訳で、2年もしないうちに、このかわいいHermesBabyかなタイプはお蔵入りとなった。思いついて物置から引っ張りだしたのだが、今となっては、限定1000台のけっこう文化資料的かつ希少価値がある無用の代物なのかも知れない。
