なんで山登らへんの 第18回 1996.10.1
体験的やまイズムのすすめ
![]()

![]() いまから数えてもう十数年も前のことになりますか。そのころ急に右腕が上がらなくなりました。腕を上げようとすると肩に激しい痛みが走ります。
いまから数えてもう十数年も前のことになりますか。そのころ急に右腕が上がらなくなりました。腕を上げようとすると肩に激しい痛みが走ります。
バイクで走っていて、ピースサインの対向車にVサイン、「アイター」とバイクがよろけ、こけそうになる。
「どうやら四十肩らしい」と言うと、「五十に近いのだから五十肩でしょう」といわれたものでした。
この五十肩、医者にいっても針灸に通ってもなかなか治りません。もう岩登りもできんのかな、と思い始めた頃から快方に向かい始めたようでした。
ちょうどそのころの夏の終わり、剱沢から電話が入り、「ぼく暇になりましたし……」。
教え子で京大山岳部員のタケダ君からで、
「よっしゃ分かった」とぼくは二つ返事で、
「テント張って待っててくれ」とザックに一升瓶2本とつまみを詰め込むと汽車に飛び乗ったのでした。
剱沢のテントでは、毎日まいにち酒を飲み、話をし、そして眠る。飽きもせずにこれを繰り返していると、あっという間に3日ほどが過ぎました。
「どっかいかんと身体がなまってきますねぇ」
「そやなあ。まあそう急ぐこともないやろ。おまえの嫁さんの話も済んでないしなあ」
彼のガールフレンドは、高校の同級生で銀行勤務ですから、おまえは学者になりそして彼女が勤めを続けたらヒモとしては一流やと説くつもりだったのですが……。
次の年、彼はブータンに遠征することになっていました。ぼくは毎日のように、遠征隊で死なない方法を語っていたようです。きっとこの前のコングールの悲劇の記憶がまだ生生しかったからなのでしょう。
ずっと晴天で、眼前には源治郎I峰がその美しくそぎ落ちた平蔵側フェースを見せていました。
ようやくぼくが腰を上げたのは、4日か5日目だったと思います。目指したのは源治郎I峰上部のクラシックルート・名古屋大ルートでした。
「わし、あんまり調子ようないしリードしてや」
岩登りを教え込んだ教え子にリードされて源治郎I峰上部フェースを攀る。ぼくはある感慨を覚えていました。この壁には思い出と因縁があったからです。
ぼくがまだ駆け出しの頃のこと。けっこう自信過剰のぼくは、当時ではこの上部岩壁のただひとつのルートで、そして拓かれてまだ間もないこのルートを攀ってみたいと思ったのでした。
先輩のオナベさんに「ぼくがトップをやりますから一緒してくだはい」と頼みました。
真砂沢合宿が終わりに近づいたある日、ぼくたち二人はもうすっかり減った劔沢の雪渓をゆっくり登って行きました。
源治郎尾根の末端の取り付きで休憩んだとき、オナベさんはぼくの顔をのぞき込むような感じで、「タカダ、ほんまにゆくんけ」と聞きました。
彼はきっとぼくの不安とためらいを見て取ったのかも知れません。ぼくは「いきます」と答えました。
源治郎尾根の藪をこいでから、源治郎の縦走路と別れ、中央バンドをたどります。
取り付きとおぼしきあたりで、ぼくが、のけぞるように上方を窺っているとき、オナベさんは再度、さっきと同じ問いかけを繰り返したのでした。しばらく考えてから、
「止めます。帰ります」
今度は、ぼくはそう答えました。
「取り付きでためらいがあったら即止めるんや」という、何度も聞いたある先輩の言葉が頭をよぎったからです。
*
それから15年ほどたったある夏のこと。
その頃ぼくは、例年のように、まだ若かった奥さんや幼い娘・息子と剱沢小屋で合流するのが常でした。
高校生の合宿は大抵の場合、縦走してきて剱で終わり。つづいて文部省の登山研修所のインストラクターのスケジュールに入ります。この順序が逆になることもありましたが、とにかくこの二つが済んで、ようやくぼくは家族とともに何日か、天上のように涼しい剱沢の生活を満喫するのでした。
そうしたある日のこと、小屋の友邦の仲間で、顔馴染みのホシノ君が「中谷ルートに行くんですが……。行きませんか」。
ぼくは、ホシノ君とチバ君に連れられて、下部岩壁中谷ルートに出かけたのでした。
最初の棚までの凹角は、急なフリクションクライムで、リードするチバ君は「ひゃー、いぼ痔が出そう」と奇声を上げながら登り切りました。
上からパラバラ石が降ってくるので、見上げると、先行パーティのセカンドが岩に張り付いたまま動けなくなっており、岩を掻き落としているのです。ぼくは、富山弁で、
「こらーっ。なんとかいえーっ。どこのもんじゃー」と怒鳴りました。
遥か上から「すみません。京都でーす」というトップの声がしました。セカンドは声も出ないくらい必死のようでした。
草付きを、五本の指を熊手のように突き立てる指かんじきで登ると、外傾したバンドになりました。
このバンド、平蔵雪渓側に大きく外傾した、つるつるのスラブで、おまけに急傾斜で下っているのです。
チバ君が、「こうするんです」といいざま、「ヒヘー」と、奇声を発しながら、そのスラブを一気に駈け下り終端に走り込みました。
一歩一歩のフリクションを利かすには、あまりに急すぎるかんじで、ぼくは膝のふるえを押さえ深呼吸してから走ったのでした。
でも、ホシノ君ががっちり確保してくれているはずで、ぼくはなんだか保護者に連れられて遊園地に来た幼稚園児みたいな気分になっていました。
だから、人工のピッチで残置のシュリンゲが切れて、30cmほど墜落したときも、不思議にその感覚を楽しんでいたのです。最後あたりのチムニーで、空の一部がスリット状に見えるだけの不気味な暗黒のルートも、極めて新鮮だったのでしょう。
ぼくは、手ぢかに味わった上質の満足感とともに、源治郎の尾根道を下りました。そして、剱沢雪渓を交互に吹き下ろす生暖かい風と冷たい風に頬をなぜられながら小屋への帰路をあえぎ登ったのでした。
*
 さて、そういうわけで、今回タケダ君とゆく上部フェースは、考えてみれば学生時代からの、15年以上も蓄えていたルートということになります。
さて、そういうわけで、今回タケダ君とゆく上部フェースは、考えてみれば学生時代からの、15年以上も蓄えていたルートということになります。
そして、これで源治郎I峰平蔵側フェース下部と上部岩壁が繋がることになるわけです。
それにしても、一年以上も使えなかったので、右腕は衰えきっているはずです。そんな身体で、核心部のバングが越せるだろうか。ぼくは少々心配でもありました。
そうとう早出したはずではあったのですが、それでももう剱の一般ルートに向かう人たちはとっくに出払って、閑散とした剱沢のキャンプ場を後に、ぼくたちは剱沢雪渓にくだって行きました。
どうした訳か、このときのルートの記憶があまり明瞭でないのです。たぶんタケダ君に任せ切った感じになっていたからなのではないかと思います。
ぼくがはっきり覚えているのは、核心部のバングの乗り越しだけです。たぶん一番気がかりの部分だったからでしょう。
だいたいハングの乗り越しというのは、トップよりむしろセカンドの方がしんどいのです。トップはザイルを使って自分で吊り上げられますが、セカンドはそうは出来ない。またナッツやあぶみなどの回収もけっこう大変です。
腕力の衰えを自覚していたぼくは、大小さまざまのシュリンゲを用意しました。これをあぶみ代わりに使ってやろうと考えていました。
それにグリップフイフイと平テープで作った小シュリンゲ。これを使えば握力をセーブできるはずです。
これらを使って予想以上にすいすいとハングを越えたぼくは、悦に入りすぎてシュリンゲの回収を忘れるところでした。
バングを越えると圧倒的な高度感で、細かいホールドースタンスのきれいな壁が延びていました。
小さな足がかりに爪先で立ち、深呼吸をしながら身体全体を空間に押し出すと、ぼくはなめるように上方に移動して行きました。
確保しているタケダのそばまで這い登ったとき、彼は真剣な顔で、
「せんせ、急いで。ぼくウンコがしたい」。
「もう我慢できひんのけ。ここでは無理やで」
あと1ピッチでブッシュに入れるようです。でも、そこで彼がウンコをしたら下で確保するぼくはそれをかぶる危険性もある。
「もうちょっとここで我慢しとれよ。わしが登るし」
そういって、ぼくはリードすることにしたのでした。
そしてようやく達した這い松のブッシュで、タケダ君は用を足します。しかし次のピッチでまたも、
「あかん、あかんまたウンコや。せんせザイル張っといて下さいよ」とズボンを下ろそうとするので、
「そんなルートの真ん中は駄目やぞ。左のブッシュに入れ」と下に向かって怒鳴ったのでした。
念願のルートを一気に登り切った感じで、解放感と成就感ですっかり高揚感に満たされたぼくは、「うんこたれルートも終わりに近づきました」とふざけながら、稜線に向かって這い松をこいでいったのです。
*
昨年の暮れ、たぶん北山パーティのすぐ後だったと思うのですが、タケダ君から一通のファクスが届きました。懸案の還暦イベントの相談がしたいとのことです。
もう何年も前から、彼は時折わが家に現れると、きまって「還暦にはマッターホルンに登ってもらいましょう」というのが常でした。
そして酔いが回るとともに、一人で勝手にはしゃぎだし、「マッターホルンの頂上で赤いちゃんちゃんこ着て、マリア像にキスをして、それが山渓のグラビアを飾る。いやあ、面白いじゃないですか。ははは。はははっ」と大騒ぎです。
これはきっとひどいストレスのせいやなあ。バブルが崩壊したら大学の先生も大変なんやろか。なんとなくそんな気もしていたのでした。
還暦パーティなどというものは、やってもらう本人はあんまりうれしいもんではありません。会社などでは、まだ十分働けるのにもう引退しないといけないという気にさせる働きがあるのかもしれませんが……。祇園の女将さんなどは、「そんなもん、止めとおきやす」と口をそろえていったものです。
「いやちがうんや。わしの還暦やゆうたらそれを口実にしておけんたいで遊びよる奴ががようさんおるんや」
ぼくはそう弁解していたのです。
それにしても、マッターホルンに登らされるのは絶対にいやでした。この歳になってあんなしんどい山に登るのはぼくの主義に反するという気もしました。
ぼくが高校生の頃、首っ引きで読んだ本の一つに、エドワード・ウィンパーの『マッターホルン登攀記』がありました。その当時ウィンパーはぼくにとって憧れの人であり、マッターホルンは山というよりもっと偉大ななにかのように感じていたような気がします。
スイスの山に登るのは賛成。でもそれは楽に登れてワインで乾杯してほろ酔いで下れる山でないとあかん。ぼくはそう勝手に決めていました。
還暦パーティ準備会の当日、タケダ君を筆頭に6人が集まりました。どうした訳か、彼はマッターホルン案を引っ込め、東南アジアのどこかの島で現地集合での正午から始まって夜半に及ぶパーティを提案したのです。
他の連中はパーティそのものには賛成、でも場所を変えるべきだということになりました。中央アジア、スロバキア、カナダなどがあがっているとき、誰かが「バイクでヨーロッパを走ったら……」といい、一気に「それ、それ、それだ」ということになったのです。
*
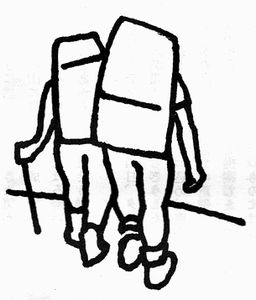 ヨーロッパをバイクで走るということになると、どうしてもシンプロン峠を越えてイタリアに入りたい。
ヨーロッパをバイクで走るということになると、どうしてもシンプロン峠を越えてイタリアに入りたい。
何年か前、アムステルダムから車で、スイスを経由してプラハに向かったとき、シンプロン峠を越えました。その時何人ものライダーたちが、峠のワインディングロードを軽々と駆け技けて行く様を見て、いつかここを走りたいと思っていたからです。
ぼくがシンプロン峠を越えてイタリアヘ向かう。コモ湖の畔で休憩する」というと、タケダ君が「アルプス越えで地中海へ」と叫びました。
するとあの時同行していたシノハラが「真っ直ぐに進んだらベニスよ」とつぶやきました。そうか、ベニスか。ベニスは最高や。パーティはベニスでやろう。こうして場所はベニスに決まったのでした。
その後の調査の結果、色々問題点が出て、計画には変更が加えられました。
まず、バイクのレンタルは、アムステルダムでしかできない。そこからシンプロン峠を越える日程を組むとなると一日に600kmは走る必要がある。これはちょっときついということになったのです。
でも最大の状況の変化は、パベルの事情でした。彼はぼくの親友のバイカーで、ぼくたちのバイクツーリングに参加するためだけで、来日したりもしているのです。ヨーロッパのバイクツーリングでは彼の参加が前提となっていました。
ぼくが、8月6日にベニスでパーティという予定を知らせたとき、すぐに来た返事のファクスにはこう書いてありました。
何という偶然の一致だろう。全く同じ日に、ぼくとポーリンは結婚する。この日はまた、私たちの家族のチェコからの亡命の記念日でもある。この記念日にチェコ人とオランダ人が結ばれるのは意味あることであると考えている。どうか君のパーティの日取りを変えてぼくの結婚式に参列して欲しい。
ぼくは、そういう事情で準備に協力できない。結婚後も5週間のハネムーンに出かけるので、出来ることはするけれど、ぼくの協力を期待しないで準備して欲しい……。
こうなると、やはりシンプロン越えは無理だと考えざるを得ませんでした。
結局、空路でベニスに直接入り、パーティを済ました後アムステルダムに戻り、レンタルバイクを借りて、数日のツーリングを行う。そういうことに計画を変更したのです。
参加者がすべてライダーではないのだから、ツーリングの比重が軽くなるのも致し方のないことだと納得したのです。
言い出し兵衛のタケダ君の事情も変転きわまりなく変化していました。彼は学者として海外援助計画などに関わっているので、とても忙しいのです。連絡は殆ど海外とのファクス交信となっていました。
彼は自分の最初の提案の現地集合の部分だけは保持しており、ベニスヘも一人後から合流する予定でした。
*
パベルがアムステルダムの日本のエージェントを紹介してくれました。京都にも支社があって便利だろう。自分も会ってきたけれど彼らもがんばってやるといっているから使ったらどうかという事だったのです。
ところがこの有名なエージェント、極めてレスポンスが悪いのです。問い合わせをしても素早い的確な応答がない。
レスポンシビリティには責任とか信頼性とかいう意味がありますが、もともとの意味はレスポンス出来る能力ということで、これを欠くエージェントなどはどうしようもないのです。
いっこうに話が進まず、いらいらしている頃、またパベルの状況が変わりました。結婚式の日取りが大幅に早まったのです。ポーリンが妊娠していることが分かり、結婚式が2ヵ月ほど早くなったのです。
ぼくはこれに出席することになり、準備は現地で行える見通しが立ちました。この結婚式の模様は、先の号で書いたとおりです。
現地に飛んでこのエージェントとも直接接触し、いろいろと理解が深まりました。
たとえば、コンセルトヘボウの予約を尋ねると、夏の間は演奏は行われませんという話。でもこれは大間違いで、夏の間には保険会社の寄付で、通常の半額の2500円でほとんど連日の演奏が行われているのでした。
ベニスでのオペラ『蝶々夫人』の予約に関しても、ロンドンの予約センターに聞いてみますというだけで、後が続かない。せっついたら、自分でやって下さいと、電話番号のリストを送ってくる始末です。
ところが、ぼくが自分で予約する予定のアムステルダムのホテルに、日本に帰ってから問い合わせると、ただちに返事が来て、「ここからは無理。ベニスのホテルのコンシアージに頼みなさい」。何とも明快なのです。
帰国する前日、通りすがりに入ったレストランが大変よかったので、着いた当日のための夕食の予約をしておきました。日本に着くと、すでに予約承りとメニューの再確認のファクスが着信しているという具合なのです。
ところがこれに反して、かたや極端にいえば調査能カゼロ、レスポンス皆無という感じです。ゼロ・皆無というより、もともとお客の意向を受けて働こうという気がないようなのです。コンサルタントによってビジネスするのではなく、情報は与えずサービスですなどといいながら儲けを上乗せする。その代金もクレジット払いは駄目で当方のレートを使うというのでは、よくない利鞘稼ぎとも取れそうです。でもこれらはまさしく日本の会社の独自性であるという気もしたのでした。
結局、大きな無駄な回り道をした後、ぼく自身がパベルと相談しながらすべての準備をすることになったのでした。
パベルは「ぼくたちは大いに勉強したことになる。これからはナオキパベルエ-ジェントで行こう」とファクスしてきました。
唯一残念だったのは、タケダ君が参加できなくなったことでした。それで結局参加人数は16名となりました。そして、この計画が始まって後、ぼくは相次いで結婚の仲人を頼まれ、その3組のハネムーナーはすべてこの一行に含まれていたのです。
かくして、ベニスでの還暦パーティの主賓は、一転してベニス新婚ツアーのツアーコンダクターとなってしまったのでした。
新婚ツアーに安ホテルというわけには行かず、すべては五つ星です。僕はエ-ジェント抜きの利点を生かしてうんと安く泊まれるように努めました。
7月25日、10cm厚ほどにもなったヨーロッパとの交信ファクスのファイルをかかえて、僕は一行とともに関西国際空港を飛び立ったのでした。
