なんで山登らへんの 第22回 1997.2.1
体験的やまイズムのすすめ
![]()

 縦走というのは、山頂と山頂をつなぐ山登りの方法です。
縦走というのは、山頂と山頂をつなぐ山登りの方法です。
ヨーロッパの高山、ヨーロッパ・アルプスの場合、縦走はより難しく、だから初縦走が行われるのは、それぞれの頂の初登頂が行われた後のことだったようです。
日本の高山、日本アルプスでは、氷河はなく、樹林限界を抜けたばかりの山なので、初登頂などということは、日本登山界の記録以前に行われてしまっていました。
奈良時代に伝えられたという修験道の行者は、燃えるような宗教心を持って、日本アルプスの高山の頂を目指しました。さらにはもっと以前から、そこアルプスの山域は衿羊や月の輪熊あるいは野兎を狩る猟師たちの活動の場でした。
3000m近い連山の峰々を辿るというような山登りは、山頂近くまで樹木があって可能だったといえるでしょう。
もう40年ほども前、ぼくが大学の山岳部に入った時の顧問のガメさんは、今西錦司の先輩だったという名物教授でした。彼は、ぼくの北アルプス縦走計画を見て、
「縦走か。そらええわ。わしら昔はなぁ、おめぇ。あのへんは行ったり来たりで、山の上になん週間も居座っとったもんや」
「食うもんヶ、そんなもんおめぇ、人夫にゆうたら味噌やら米やらなんでも麓から担ぎ上げて来よる」
日本の山では、3000mの稜線といえども、這い松の下に潜り込み、油紙をかぶっただけで、雨露をしのげたのだそうです。
さて、ぼくの最初の北アルプス合宿計画は次のようなものでした。
まず、上高地をへて、穂高岳涸沢に入り、10日間ここで岩登りを行う。その後、槍ヶ岳をへて剱岳まで縦走する。
縦走はいったん横尾まで降り、そこから槍沢を登ることから始まりました。たぶん重荷を背負っての大切戸の通過を敬遠したのだと思います。
横尾、坊主の岩小屋、双六、黒部五郎、太郎兵衛、数合、五色が原と泊まりを重ね、剱沢に至りました。
その当時、テント指定地などはなく、水場が近くて見晴らしの好い奇麗な場所なら、どこでも好き勝手にテントを張りました。薪は這い松の茂みに潜り込んで、枯れ木を探したものです。
あの時はたしか、太郎兵衛平の草原で、日が落ちました。しかたなくぼくたちは、夕映えの残照に、鏡のように白く光る小さな池塘の畔にテントを張ったのです。
飯食の飯が炊きあがり、食器に盛りつけられた飯を受け取った一人が、歓声を上げました。
「へえー。今日は赤飯けえ」
炊事当番が、「あほか。アカメシなんか炊いてへん」
よくみると、池塘の溜まり水にいたミジンコ飯だったのです。
「ミジンコも蛋白源やんか」とやせ我慢をいいながら、ぼくたちは、この赤ご飯を喰らったのでした。
こうした調子で、のそのそと、山のような重荷を背に歩くぼくたちを、軽快な足取りで、追い越して行く小さな荷物の登山者がいました。小屋泊りの人たちでした。
この時の縦走コースは、とても印象的で、ぼくの気に入ったのでしょうか、有峰から太郎兵衛平を経由して剱沢までというのは高校山岳部の合宿の定番コースになりました。また剱岳での合宿後、薬師岳を越えて黒部源流に至り、そこで解散というのは、大学山岳部お決まりの道順で、ぼくはいつも監督として同行したのです。
こうして、毎年のように何度となく北アルプスの稜線を往き来しながら、ぼくがいつも憧れていたのは、軽い荷物で、小屋泊りの縦走をしてみたいという事でした。
*
桂高校山岳部のOBで、いまは食糧庁に勤める教え子のとっつぁんが、
「あのですねぇ。たかぁセンセゆうたはった夏山はどうなりました?」
あれは1992年、たしか7月の中頃のことだったと思います。
とっつぁんにそういわれて思い出したのですが、たしかにぼくには記憶がありました。
「縦走やったら行ってもええなあ」とそういったことがあったのです。
それはその年の6月、ロンドンでのコンピュータ・カンファレンスに出かける前のことでした。ロンドンからスイスそしてプラハを回って帰国したぼくを、とっつぁんは待ちかまえていたかのようでした。
ぼくが「縦走やったら……」といった裏には理由があったようです。ひとつは、三十年来の夢である「小屋泊りでの縦走」の実現。もうひとつはパキスタン・ディラン峰再訪のための足慣らし。
実はこの年の9月、家族を連れて、ミナピンピークのベースキャンプまで登ることを決めていたのです。
ところで、とっつぁんが、「あのですねぇ」と切り出したときは、とてつもなく驚異的にしつこいことを、ぼくは経験的に知っていました。だから、8月のバンコック行きの予定を出来るだけ繰り上げ、8月21日から31日までの10日間で、槍―劔の縦走をすると決めねばならなかったのでした。
もうひとり、とっつぁんの先輩で、ぼくの会社の社員のトモが行きたいといい、縦走のメンバーは3人になりました。
さらに、日程的に縦走は無理だけど、槍ヶ岳まで同行したいと、ぼくの昔の同僚顧問で、バイクやコンピュータ仲間のイノウエ君と、とっつぁんの後輩の2名が合流してきました。
彼ら2人の介添えがあればセキタも行ける。そう考えて、ぼくはセキタを誘うことにしたのです。彼はこの年の4月、腸の腫瘍を取り去る手術をしたばかりでした。
彼は良性のものだといっていましたが、ぼくは信用せず、タカヒコドクターに密かに調べるように依頼したのです。
タカヒコは病院を訪れ、執刀医に会い、切除部の保存標本も見ました。腫瘍専門の彼の報告では、手術は完璧と言っていいが、転移の可能性は50%はあるというものでした。
「わし、この夏の終わりに、槍から剱まで行こ思うてるんやけど、槍まで一緒に行かへんケ」
セキタは、すぐに「行きたい」と答えました。
でも、当然の事ながら、彼の奥さんは猛反対でした。彼の主治医も、「過激な運動はいけない」とやはり反対したのだそうです。
ぼくは、タカヒコドクターに、奥さんを説得するように依頼し、そこでタカヒコは、「いやあ、足で歩いて登る山登りはそんな過激な運動ではないですよ」などといったのだそうです。
ぼくがセキタを誘った唯一の理由は、もし腫瘍が転移していたら、これが最後の山になることもあり得る。そう思ったからでした。
*
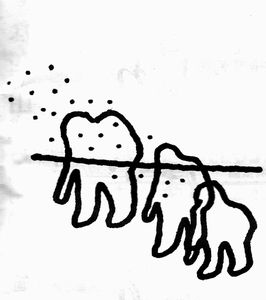 京都駅前で上高地行きの夜行バスに乗った一行6人は、翌朝上高地着。考えてみれば、ぼくは20年以上ももっぱら剱周辺一辺倒で、この辺りには足を向けていなかったのです。
京都駅前で上高地行きの夜行バスに乗った一行6人は、翌朝上高地着。考えてみれば、ぼくは20年以上ももっぱら剱周辺一辺倒で、この辺りには足を向けていなかったのです。
小雨が降り、見上げても山の眺望はききません。雨具を着けるほどのこともないと、ぶらぶらと歩き出しました。
昔のままの河童橋を過ぎます。その下を流れる独特に青みがかかった清流も昔と変わりません。今日びの日本の川で、20年前と同じというのは、なんだか不思議な気もしました。
そして、下界の川が汚れきった大きな理由の一つに、あらゆる合成洗剤の過度の使用があるのではないかという気がしたのです。でもこの昔と変わらず清冽に見える梓川の水も、実はそう見えるだけで、本当は間違いなく汚れているに違いない。
左に聞こえる、耳に優しい梓川の瀬音を楽しみながら、これといった特徴のない道を辿ってゆきます。やがて巨大な岩塊という感じの屏風岩が見え始めると、横尾でした。
ずっとむかし、まだ20歳代のぼくとセキタはこの壁を登ったのでした。初めて登られて以来、20年間誰も成功しなかったルートを、ぼくたちは死ぬことを勘定に入れて攀じ登ったのでした(『なんで山登るねん』「氷雪の屏風岩一ルンゼは恐れと迷いとためらいを越えて」の項参照)。
その屏風岩が見えてきても、なぜかセキタもぼくも、なにも語りませんでした。彼がなにを考えていたのかは分かりません。ぼく自身は、あの時のあの行為をいま思い出として語ることが、たんとなく躊躇われたのでした。そうすることで、神聖で無垢のなにかが、一気に世俗化する。なんだかそんな気がしたのです。
少々意外だったのですが、屏風岩に限らず、この辺りにはほんとに、数限りない思い出がありました。ぼくは、そうした追憶を、なにか時には甘酸っぱく時にはほろ苦い想いで、噛みしめながら歩いていたのです。
横尾山荘の小屋の一室に落ちついて、ビールを飲むことになりました。
缶ビールはロング缶が750円、小缶が500円でした。早速ぼくの癖が始まって、容量をチェックします。ロング缶は500ml、小缶は350mlです。
「ロング缶2本で1500円。小缶3本でも1500円。小缶3本のほうが50ml多いで」
普通に考えたら、ロング缶が徳用で安いように思うのですが、案に相違して、そうではなかったのです。
ぼくたちは、小缶を大量に買い込み、とっつぁんが持ってきた各種の京つけものをつまみに、酒盛りを始めたのでした。
*
ぼくが、密かに、大変気にしていたセキタの体調はとくに問題はないようでした。わずか4ヵ月前に正中線を右にはずして真縦に30cm近い腹切りをしたとは思えない感じです。
胃潰瘍で吐血して入院したにもかかわらず、病院を抜け出して、屋台で飲んでいたとか、盲腸の手術の傷がひっつかないうちに岩攀りに出かけ、傷口が開いたとか。山の連中には、そういう無茶をする人が多いようです。でもセキタの湯合は、そういう例には入らないとぼくは思っていました。でもやはり気になってはいたのです。
翌日、槍沢の長い登りを、ひょいひょいと軽快に登る彼を、よたよたのそのそと登るぼくは、ずっと観察し続けたのでした。その結果、坊主の岩小屋のあたりまで来て、とうとうぼくの方がばててしまったのでした。
肩の小屋に達し、回復の自信にあふれている感じげセキタを見て、ばててよれよれのぼくは本当にうれしかったのでした。
初めて泊った肩の小屋の、フルートの生演奏とはあまりにそぐわぬ、すしづめのかいこ棚は、閉口の極みでした。
翌日は、雨になりました。でももう一晩泊る気にはなりません。
飛騨側へ白出沢を降って下山するセキタやイノウエ君たちと別れ、ぼくはとっつぁんとトモと一緒に猛烈な風雨の西鎌尾根を双六小屋に向かったのでした。
風雨にあおられながらたどり着いた双六小屋は、殆どお客もなく閑散としていました。ぼくたちは、煎餅布団にくるまって、濡れそぼち冷え切った身体を温めたのです。
双六岳に登れば、広く広がった頂上の草原に点々とある露岩には、大きな岩茸が付いているはずでした。今日のような日には、雨にふやけた岩茸は採りやすいのですが、昔のように採りに行く気にはなりませんでした。
翌日も天気ははかばかしくなく、出発を延ばしながら様子見をしていました。昼前になって晴れ間が出てきたので、黒部五郎を目指して出発することにしました。
この辺りで、ルートは三俣蓮華小屋や後立山に向かって三俣蓮華岳を低くまくものと、稜線に上がるものとに分かれます。
最初にここを通ったとき、三俣蓮華頂上付近で、ぼくはルートを失い、みんなを待たして単身偵察に出かけたことがありました。見晴らしの利くところを求めて、お花畑を斜上すると、山肌が抜けたザレ場に出ました。見るとそこには点々と足跡があり、ザレ場を横切っていました。ほっとし、勢い込んでそのトレールを伝って行き、フッと前を見ると、そこには可愛いぬいぐるみのようた小熊を連れた月の輪熊が、「なにしについてくる」という顔で、振り返っていたのです。
三俣蓮華岳の樹林帯の急な下りを延々と続けると五郎沢乗越に降り立ち、そこに黒部五郎小舎がありました。
稜線とはいえ、そこはまぎれもなく黒部の源流で、ぼくはわが家に帰ったような安らぎに満たされていたのです。
*
翌日は雨でした。願ってもないことです。ぼくは源流の雰囲気を楽しむために一日停滞を決めました。
昼頃雨が上がり、ぼくは岩魚釣りに出かけることにしました。竿は小屋オーナーの小池さんから借りました。
草原を雲ノ平の台地に向かって進み、細流を飛び石伝いに降って行くと、沢が急速に落ち込み、大きな岩いわゆるゴーロが積み重なった急な沢になります。これがいわゆるゴーロ沢、五郎沢の由来なのであります。
本流まで一気に降り、毛針を振ったのですが、全く当たりがありません。たぶん釣り人が入り、釣り荒れたのでしょう。
昔はこんな事はなかった。「糸が切れて釣り落とした岩魚をあわてて掴んだら、そばの別な魚を掴んでいた」などという冗談が本当に思えるくらい魚がいたのでした。
日暮れが近づき、帰ることにしました。ところが五郎沢に入ると、どんどん釣れ、ぼくは夕闇のなかで竿を振っていたのでした。
小屋のお兄さんが出迎えに下って来ていました。小屋では、ぼくたちが右に分岐して黒部五郎に上がる沢に迷い込むかも知れないと心配したようでした。でも、ぼくにとってはこのあたりの沢は、まるで自分の掌のように分かっていたのです。
小屋に帰り着くと、ぼくの読者のおばさん集団の大歓迎を受けました。
「タカダさん。待ってたの。釣れましたか」と大騒ぎ。
「はいはい、釣れました。みなさんも召し上がって下さい」と獲物を見せながら、もし釣れていなかったらこれは大変だったなと、ぼくは胸をなで下ろす感じだったのです。
小池さんは、ぼくの18匹の形の揃った獲物を見て、「名人だね」といいました。
小池さんは、「岩魚釣りの名人」といわれているそうです。「名人」に名人といわれたぼくは「大名人」ということになりそうです。
小屋が作ってくれた岩魚の「骨酒」は、それなりに美味だったようです。
この今回の「小屋泊りの縦走」を済ましたら、もうぼくにはやりたいことがなくなるなあ、と思っていたのです。ところが、小池さんは、ヘリで荷揚げをしてあげると約束してくれました。
この小屋にワインやうまいもんをどんと上げて置いて、このあたりのいい場所で小屋掛けをして岩魚を釣る。これが次の目標になるなあ。そんな気がしたのでした。
翌日は、黒部五郎のカールを詰めて稜線に至り、延々と続く高原状の山並みを辿り、太郎兵衛平の小屋まで進みました。
*
 太郎の小屋から数合の小屋、数合の小屋から五色小屋へと泊まりを重ねてゆきます。
太郎の小屋から数合の小屋、数合の小屋から五色小屋へと泊まりを重ねてゆきます。
ぼくたちの出発はどうしても遅い。自分ではいっこうに遅いとは思わないのですが、他の人たちは暗いうちに出発するようで、ぼくたちが起きた頃には、もうだれも居ません。そして、小屋に着くともうほとんどの人は食事が終わっている。でもぼくにしてみれば、そうして少し時間をずらして歩く方が、より静かな山が楽しめるという気がしていました。
早立ちする人々、特にオバタリアンが大声でわめき散らして出発して行くのには、ほんとに悩まされました。布団をひっかぶってじっと耐えている分だけ、なお出発が遅れるのでした。
ただ一ヵ所だけ、ぼくが早立ちしようと思ったところがありました。それは、数合の小屋です。小屋を出て降って行き、数合沢乗越、そこから数合の頭への登りになり、これを越えると、越中沢岳への急な登りになります。この辺りは、実は雷の通り道なのです。ここでは、何度か恐ろしい目にあっています。午前中に通過しないとやられます。
いつもよりは早出をしたぼくたちは、わき上がる積乱雲が、こっちに向かって崩れ出すのを横目に見ながら、数合の頭を越え越中沢岳の頂上に達しました。ここで昼食を取ることにしました。食べ終わって、ミルクティーを飲んでいると、急にガスに包まれたのです。
これはやばい。ぼくは大急ぎで、斜面を駈け降りました。越中沢岳が五色ヶ原側に大きな裾野を引っ張る感じで傾斜が落ちる辺りまで来て、小さな露岩が集まっている岩の上でツェルトを被ったのでした。
すぐに雨が降りだし、目の前が真っ白になるような雷が炸裂し始めたのです。
誰でも雷をさけるには窪地が良いと考える。でもこれは誤りらしいのです。たしかに雷は高いところ尖ったところに落ちる。でも雷さんから見れば人間の高さなどはゼロに等しい。
雷は、だから山頂に落ちる。放電した巨大電流は、電気の通性として表面を伝わって走ります。山の雷で人がやられるのは、ほとんどの場合この地表を走る二次電流によるのだそうです。ぼくがこうした知見を得たのは、たしか『岩と雪』に掲載された-雷撃からの逃避-という翻訳論文からだったと思います。
窪地や洞穴の口などにいると、地表を走ってきた電流の放電を受けてやられる。むしろ、平らな場所の盛り上がった岩屑の上などに座り、二次電流がお尻の下を通過するのを期待すべきだというのです。
こうした理屈を信じておれば、何となく気が楽になるものです。ぼくたちはツェルトの中でお茶などを飲みながら、十数発の雷鳴の炸裂に耐え、雨が止むのを待って約1時間後に出発したのでした。
ゆっくりゆっくり歩いて、五色の小屋には夕暮れに着きました。
翌日、五色の小屋を出るとすぐにザラ峠を過ぎます。ザラ峠からは急な、けれどもぐんぐんと高度が上がるのが実感できる気持ちのいい登りが続きます。
雪田や雪渓を渡っては稜線を越え、そしてまた雪渓を渡り、やがて竜王の肩を過ぎると、一の越への下りです。
一の越で弁当を食べていると、夕立がやってきました。剱沢小屋への到着が遅れそうなので、小屋のトモクニに電話しました。もう完全に自分のシマに入ったという感じです。
剱沢小屋で、シャワーを使ってさっぱりし、何枚もの豚カツを平らげて、お酒を飲んだせいか、翌朝ぼくを痛風の発作が見舞いました。
県警救助隊のスギタ君が貸してくれた、ストックを手に、びっこをひきひき、それでも結構幸せな気分で、ぼくは雷鳥沢を降っていったのでした。
