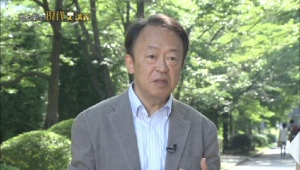スティーブ・ジョブスの顔にも少々見飽きてきました。
スティーブ・ジョブスの顔にも少々見飽きてきました。
主に使っている、ちょっと型遅れのPowerBook G4(Titanium)を立ち上げると、毎回スティーブ・ジョブスの顔が現れます。もういいわという気分になっています。
彼の死が悲しかったし残念だったのは確かなんですが。(と書いていたら、2週間続いたこの写真ディスプレーも、ようやくiPhone4Sに替わりました)
息子がSMSで「スティーブ・ジョブスが死去。なんという喪失感」と報せてきて、彼の死を知りました。病気が軽くないのは知ってましたから、意外ではありませんでした。でも、なんでジョブスなんや。ビル・ゲーツでも良かったのにという密かな思いが頭をよぎったのです。ビル・ゲーツが死んでも残念だとは思わなかったのではないかと思います。
 Apple社を作ったのは、2人のスティーブです。スティーブ・ウォスニアックとスティーブ・ジョブス。
Apple社を作ったのは、2人のスティーブです。スティーブ・ウォスニアックとスティーブ・ジョブス。
この二人の名前を挙げた時に、同時にぼくの頭に浮かぶ名前は、アラン・ケイであり、ジェフ・ラスキン、ビル・アトキンソン。
これらの人が、今のパソコンを作ったのだと思っています。これらの人はみんな天才です。