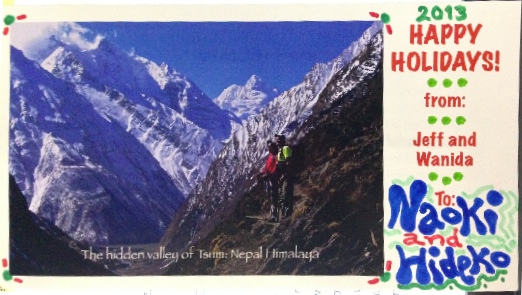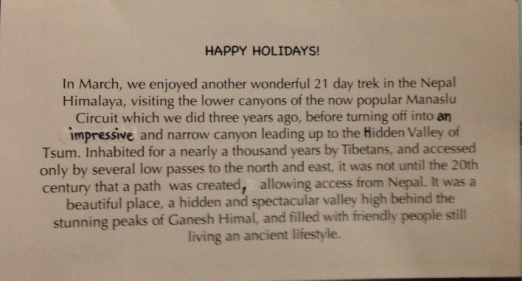ヤマケイ文庫『なんで山登るねん』表紙
『なんで山登るねん』が初めて単行本になったのは1978年3月のことだった。その後、版を重ねたが、2002年には河出書房新社から文庫本が出た。
今回の「ヤマケイ文庫」出版までに36年が経過しており、かなりのロングセラーといえるだろう。
36年の間には、この本に関しては色々のストーリーがあったのだが、そのうちの一つを紹介する事にしよう。
この本は、山と渓谷社の月刊誌『山と溪谷』の3年間の同名タイトルの連載をそのまま単行本にした物だった。連載中より若者読者から圧倒的な関心をもたれていたようだ。こんな話を聞いたことがあった。
ある人が夏山の帰り、富山駅前の喫茶店に入ったという。すると、そこに数人の高校生が口角泡を飛ばして猛烈な勢いで激論を戦わせていた。何事かと思って耳を澄ますと、『なんで山登るねん』の内容についての議論だったということだった。
続きを読む


 今回の上京の主目的は明治大学で行われた「マッキンリーから30年 植村直己を語り継ぐ」という集まりに参加することでした。別に先頃『なんで山登るねん』の文庫本化の話が山渓からあり、赤を入れたゲラ刷りの第一稿を送ったばかりだったので、第二稿を受け取りがてら寄って見るつもりでした。
今回の上京の主目的は明治大学で行われた「マッキンリーから30年 植村直己を語り継ぐ」という集まりに参加することでした。別に先頃『なんで山登るねん』の文庫本化の話が山渓からあり、赤を入れたゲラ刷りの第一稿を送ったばかりだったので、第二稿を受け取りがてら寄って見るつもりでした。