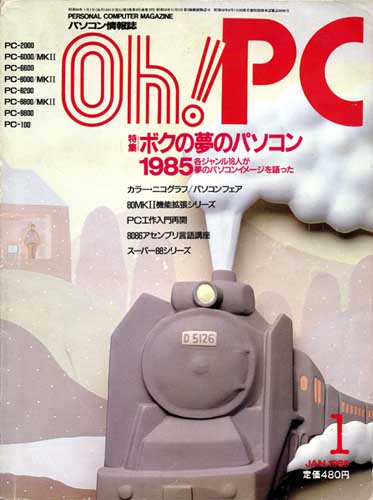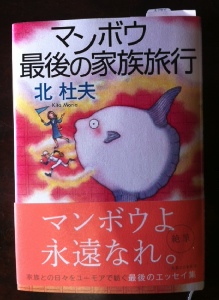何も書かなかったこの長い間に、これを言いたいということが何度もあった。けれど野暮用とかいろいろな取り込みなどが重なって、その意欲がなくなることが続いていたようだった。
昨夜のオーストラリア戦をみて、その予想に反した展開に少しイライラしながら朝になって眠った。起きだしてコンピュータを開こうとしたら、近くに住んでいる息子の嫁から「もう起きていらっしゃるかと思って」と電話があった。
「日曜はお留守のことが多いようなので、少し早めなんですが」と父の日のプレゼントにシガーの詰め合わせを持ち来った。よくセレクトされた銘柄のものたちだった。
一時間近く話をして嫁が帰ったので、さあ取りかかろうとしたら、UEFA1012欧州選手権のギリシャ対チェコ戦が始まった。これは見ないといけない。両国ともぼくには因縁のある国である。ギリシャはぼくにサッカーへの目を開かせた国であるし、チェコは旧友のパベルの国で、息子はプラハのあの天文時計のある旧市庁舎で結婚式を挙げた最初の日本人でもある。
ところで、だいたいスポーツはやるもので見るもんじゃないと昔から思っていたし、野球は嫌いだった。サッカーも、大学に入ってマラソン大会で優勝したらサッカー部からすぐに試合に出てもらいますからなどと誘いがあったが全く興味がなかった。
2002年に日本でワールドカップが開催された。当然ぼくも愛国者としてけっこう熱中してテレビを見た。ときには、会社でコンピュータの講義に使うプロジェクターをつかって、壁一面のスクリーンで観戦したりした。
続きを読む