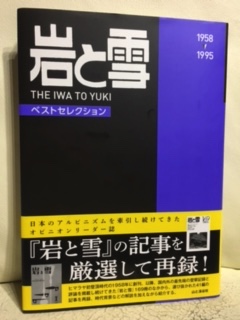
厚さは2cmすこしで、けっこう重い
むかし山登りが盛んでブームだった時代に、高級誌であった季刊誌『岩と雪』は、やがて隔月刊となり、岳界の思潮をリードしていたのですが、20年ほど前に廃刊となりました。
この1958〜1995年のバックナンバーからの選り出した論文と記録をまとめたものです。
ネットで調べると、次のような紹介が載っていました。
続きを読む

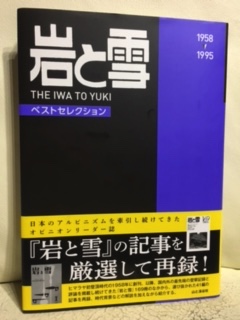
厚さは2cmすこしで、けっこう重い
先頃からWOWOWであの有名な『沈まぬ太陽』が連続ドラマWとして放送されている。
WOWOWの連続ドラマといえば、他にあの「ツインピークス」の放映も始まった。このいずれにも、ぼくはけっこう特別な思い入れがある。「ツインピークス」については別項に譲るとして、ここではあの『沈まぬ太陽』について書くことにしよう。
1965年の春のことだったと思う。ぼくは京都府山岳連盟派遣の京都カラコルム・ディラン峰登山隊の先遣メンバーとしてパキスタン(当時は西パキスタン)のカラチ空港に降り立った。
確か前年にその規制は緩和されていたとはいえ、スポーツのための外貨の持ち出しは制限されていたから、特別なルートを使って外貨を獲得しなければならなかった。
全ては今では考えられないようなことばかりだった。登山隊の装備は数トンに及び、それは半年前に神戸港を出てカラチ港に入る船便が使われた。隊員は飛行機で南回りのルートでカラチに向かう。
当時はジャンボ旅客機はなかったし、伊丹空港の周りは鉄条網の柵で、見送りの人たちはこの柵の外から手を振ったのだ。
先遣隊は本隊より半年近くも先に出発し、現地の状況を調べたり、船便の到着を待って、陸揚げを行うという任務があった。パキスタン側から同行する軍人の連絡将校と人間関係を作っておくことも重要な仕事だった。ぼくが、初めての外国であるパキスタンに飛んだのは、1965年のことだった。
続きを読む
老人は追憶の世界に生きるなどと言われるが、そういう話ではなくて、時々なんの脈絡もなく昔のことや情景が突如フラッシュバックしてくることがある。
その時、ぼくは大きな岩の上に座り、手にはピンポン球くらいの見事な石の球を手に乗せていた。
ここはどこだ。俺は何をしているのか。
そこは、黒部峡谷は上の廊下の河原で、高さ3メートルはあろうかという大きなボルダー(大石)の上にぼくは座っていた。
その時ぼくは、上の廊下から祖父沢の出会いを目指している途中で、夕暮れ時に夕食用のイワナを釣りに出かけたところだった。大きな淵があってそれが浅瀬に向かう粗砂利の斜面あたりには、大きなイワナが8匹ほど見事な編隊をなしていた。イワナたちは頭を上流に向けたまま綺麗な隊列を組み、右に左にと悠然と移動しながら遊弋を続けていた。
後ろから近ずいたぼくは、最後尾の一匹の尾ひれの右下あたりに黒い毛針を打ち込んだ。イワナはすぐ反転して毛針を追い、飛びつくのとぼくが引き抜くのとは同時で、大イワナは高く空中に舞った。
こうした場合、こんな風に最後尾から釣らないと全部を手にすることは無理なのだ。もし、前の方の一匹を釣り上げたとすると後の奴らはもう毛針を見向きもしなくなる。引き抜かずにもがかせでもしたら、みんな大慌てで深みに散ってしまうのだ。どうやら「痛い。痛い」わめくらしい。
続きを読む

『難波金融伝 ミナミの帝王 待つ女』の後半のある喫茶店の場面。左側のポスターに注目!

木曽の御嶽さん
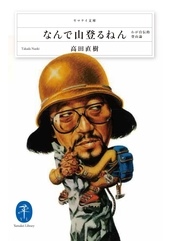
ヤマケイ文庫『なんで山登るねん』表紙
この本は、山と渓谷社の月刊誌『山と溪谷』の3年間の同名タイトルの連載をそのまま単行本にした物だった。連載中より若者読者から圧倒的な関心をもたれていたようだ。こんな話を聞いたことがあった。
ある人が夏山の帰り、富山駅前の喫茶店に入ったという。すると、そこに数人の高校生が口角泡を飛ばして猛烈な勢いで激論を戦わせていた。何事かと思って耳を澄ますと、『なんで山登るねん』の内容についての議論だったということだった。
続きを読む
東京に来て一週間ほどが経ちました。
来た頃は、これはいつものことなのですが、地下鉄に乗っている時なんともいえぬ不安を感じます。
今地震が起こったらどうしよう。とりあえず地上に逃れたとして、どっちに逃げたらよいのか、まったく分からないのです。
でもいつものように、これも一・二日で慣れてしまって、なんとも感じなくなったようです。
何年も来ていなかったので、いろいろ会いたい人があり、旧交を温めているうちに日が過ぎました。
 今回の上京の主目的は明治大学で行われた「マッキンリーから30年 植村直己を語り継ぐ」という集まりに参加することでした。別に先頃『なんで山登るねん』の文庫本化の話が山渓からあり、赤を入れたゲラ刷りの第一稿を送ったばかりだったので、第二稿を受け取りがてら寄って見るつもりでした。
今回の上京の主目的は明治大学で行われた「マッキンリーから30年 植村直己を語り継ぐ」という集まりに参加することでした。別に先頃『なんで山登るねん』の文庫本化の話が山渓からあり、赤を入れたゲラ刷りの第一稿を送ったばかりだったので、第二稿を受け取りがてら寄って見るつもりでした。
明治大学には「リバティー・タワー」という23階のビルがあって、上記の会はこの8階で催されました。二百数十人収容のホールで少しの空席もあったから、たぶん150人くらいの参加者だったのではないかと思いました。
続きを読む
涼しくなってきたので、ようやく書架の整理を始めた。
なけなしの退職金を投じて建て増しした書庫棟は三方が高天井までの書架になっていて、ぎっしりと本が詰まっている。しかしそのほとんどが、もう何の役にも立たないものなのである。一方を埋めるコンピュータ関係の英書は、パラパラページをめくると、それなりの感慨を催すだけの代物となっている。
雑誌に関しても、コンピュータ、PC関係のものとMAC関係のものだけでも膨大な量で、これに山の雑誌が加わる。
頑張って整理などしなくても、ボックリくたばったら、息子か孫がひどい男と罵りながら片付けるだろうと、不逞な考えを抱かぬでもなかった。しかし、最近やたらにネット購買した本が増えだした。これを収めるスペースの必要を感じたというわけである。
続きを読む
たぶんそれは、ぼくがまだ30歳になっていなかった頃のことだったと思う。
親父が、シラビソの樹が欲しいのだが、手に入らぬだろうかと尋ねた。庭に植えたいのだという。
シラビソというのは、ぼくの知る限り、北アルプスの2000メートルあたりに生えている、クリスマスツリーの樹で、そんなものが、田舎の家の庭に育つとは思わなかった。
シラビソは、ぼくたち北アルプスを歩き回るものにとっては、たいへん親しみ深い樹なのであった。
たとえば、夏山で有峰から薬師岳を越えて剱岳まで縦走しようとすると、薬師の樹林限界を抜けるまで、薬師を下って、上の岳から五色が原に至るまで、ずっとこの木々を見ることになる。
雪山では、その根っこは必ず枝の間が空洞になっており、非常時のビバークに都合よい場所を提供してくれるのだった。

シラビソの樹

早月尾根と早月川、その先に富山湾がある