この頃、YouTubeにはまっています。
YouTubeといってもそこにある動画は無数と言っていい訳だし、的確には表題の「しっかり学ぼう!日本近現代史」にはまっているという訳。
近現代史をぼくたちはあまり知らないといえます。その知識の大半は大河ドラマからのものだったりする。
「しっかり学ぼう!日本近現代史」は一週ごとにくくられていて、各週6話つまり、月〜土の毎日15分のシリーズです。
現在はもう第10週に入っていて、タイトルは「これがほんとの昭和初期〜大日本帝国滅亡の原因」です。そして第1話は「昭和初期の日本〜暗黒社会…ってほんと?」となっていますが、ぼくはとてもそこまでは行けず、第4週の辺りです。ここは「激動の幕末へ」です。
この週の最終第6話は「薩長同盟〜若者の志が日本を動かした」です。
このシリーズの面白いのは、通説の裏が明かされることと、いつも今日の事実との対比がされることです。
たとえば、薩長同盟は池田大作と宮本憲治に手を組まそうとしたみたいなとか、薩長同盟は西郷・大久保と木戸孝允の話し合いだけだったが、長州が幕府軍を撃退した時に始めて同盟になったとか、同盟というのはそんなもんで、アメリカが止めたといえばそれでしまいという話になります。
また「そこでこれ」とパネルがでてきて「野田佳彦、いや違った徳川慶喜」などとふざけが入るのですが、こうした喩えが極めてリアルで分かり易かったりするのです。
このシリーズは「CGSチャンネル」 ChGrandStrategyチャンネルグランドストラテジーで放映されています。
今年の4月頃から始まったようです。上の紹介の動画があるのでそれを見ましょう。
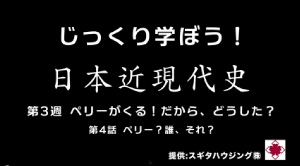 日本の近現代史は、「黒船来航」から始まるというのが常識ですが、このシリーズでは第3週の4話になって初めて出てきます。それまで、十数話にわたって、延々と諸外国の状況や世界の動きがつぶさに省察されます。世界や周囲の状況があって初めて立ち位置というか、日本が分かるという訳です。
日本の近現代史は、「黒船来航」から始まるというのが常識ですが、このシリーズでは第3週の4話になって初めて出てきます。それまで、十数話にわたって、延々と諸外国の状況や世界の動きがつぶさに省察されます。世界や周囲の状況があって初めて立ち位置というか、日本が分かるという訳です。
そして、いよいよ始まるのですが、その第3週のタイトルはというと「ペリーが来る!だから、どうした?」なのです。さらに第4話「ペリー?誰、それ」です。
ペリーは脅しにやってきたように思われているけれど、実はそうではなかった。けっこう優しい男だったようで、密航しようとした吉田松陰が罰せられることを心配して、幕府に寛大な処置を求める手紙を書いているのだそうです。
日本の侍はびっくりはしたのですが、他の国は恐れ戦いたのだけれど、日本はそうでもなかったようです。浦賀に出かけスケッチをして、どうかね作れるかねと船大工に尋ねた。作れるでしょうとほんとに作ってしまったのだそうです。日本って凄いという話がでてきます。
それにしても、マッカーサーが厚木に来た時に、ペリーの掲げていた旗を持参したというのは、果たしてどっちの意味だったのでしょうかねえ。
どうです。興味わきましたか?このシリーズ。
是非ご覧になってください。
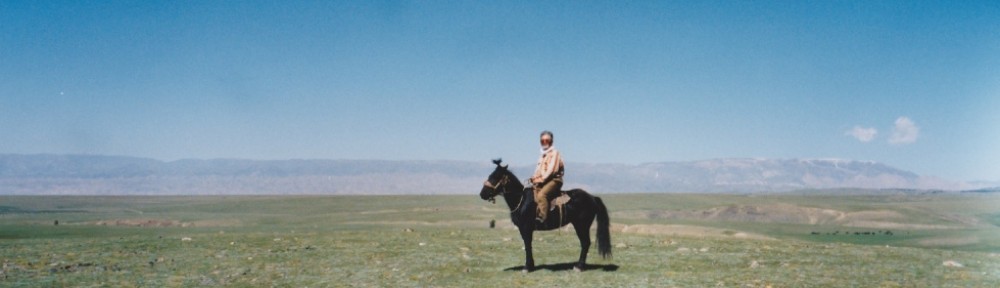
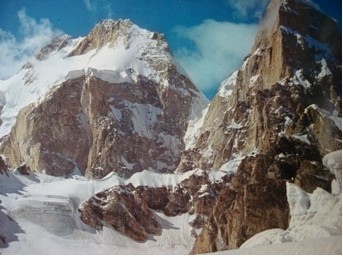
 最近なにげなくKAZUYA_CHANNELという動画サイトを見た。これがなかなか面白い。
最近なにげなくKAZUYA_CHANNELという動画サイトを見た。これがなかなか面白い。